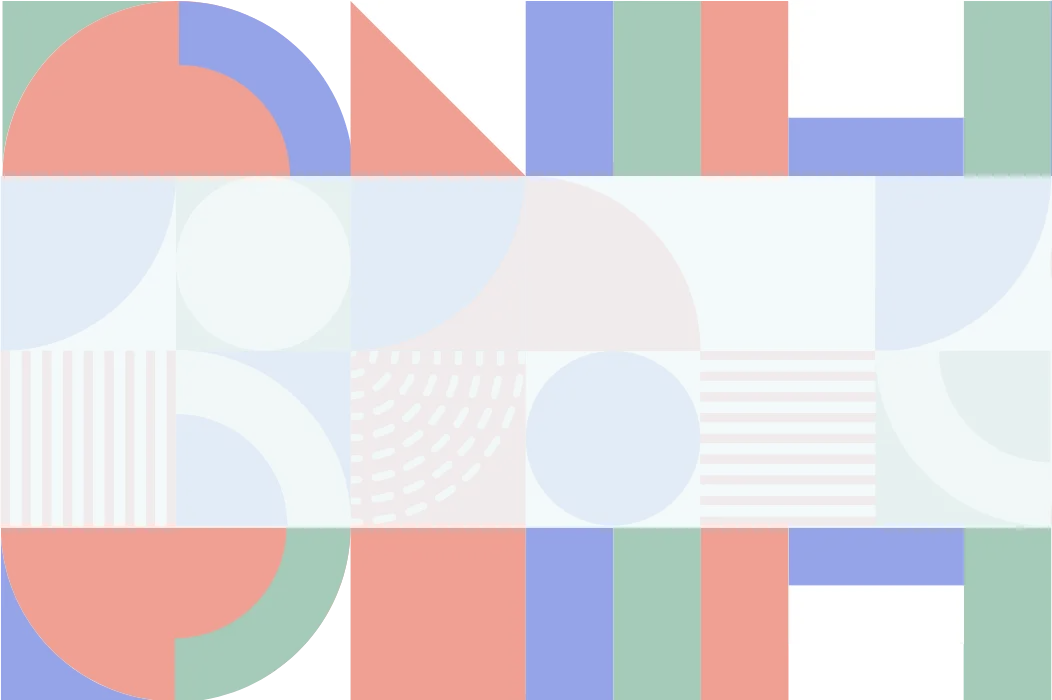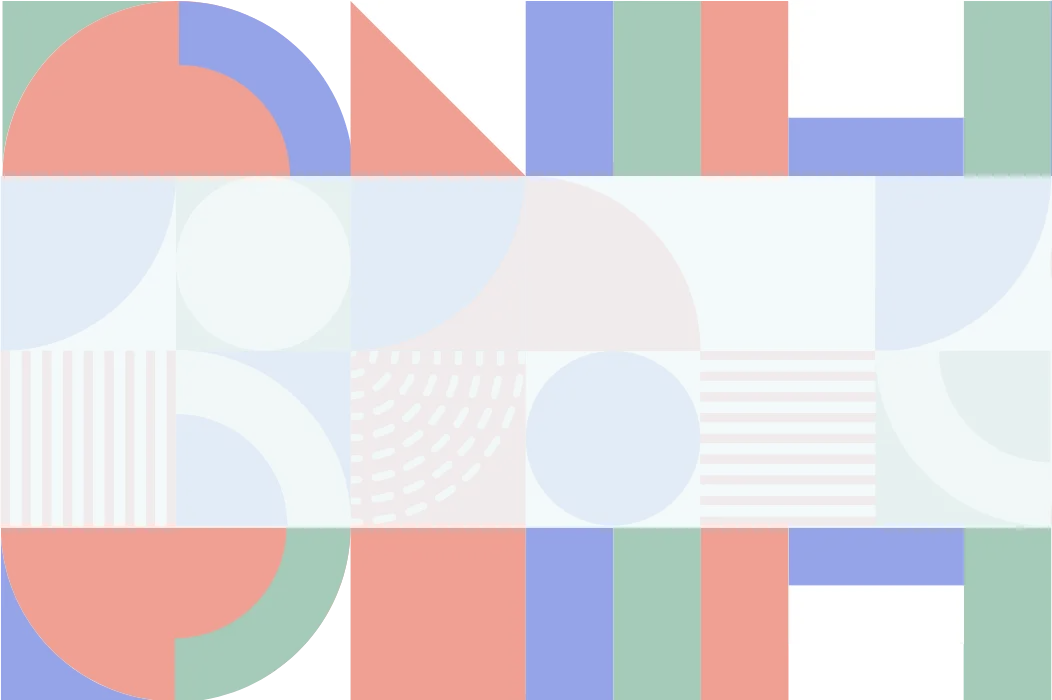| 1. |
はじめに
乳がんの増加、乳房健康への関心の高まりや乳がん検診の推進をうけ、その診断・治療において高度な技量や各専門職の長所を有機的に統合したチーム医療体制の充実が望まれています。従来の乳腺診療は外科医が主に診断から手術を中心とした治療を担当してきましたが、専門的な画像診断技術が必要なこと、治療の主体が薬物療法への変革をうけ、「乳腺学」がひとつの専門分野として認識されるようになってきました。
日本乳癌学会もその社会情勢の変化にあわせ、乳腺専門医の育成と認知を目的に、乳腺認定医・専門医制度を確立し、乳腺科の標榜ならびに専門医の広告も承認されています。
当院乳腺グループでは、年間200例を超える原発性乳がんの診断と治療、さらには進行再発乳がんの治療にも精力的に取り組み、地域の患者様から高い評価をえております。また、通常診療のみならず、診断から各種薬物療法に関する臨床試験や開発治験に積極的に参画しています。全国規模の各グループに所属し、臨床試験の立案から実施までわが国第一線での活躍の機会も可能です。さらに基礎研究と臨床応用の統合をめざしたトランスレーショナルリサーチにも全国有数の機関との共同研究を進めています。
乳腺専門医の需要は高まる一方です。当院の乳腺専門医研修プログラムは、日本乳癌学会の認定医・専門医カリキュラムに沿いながら、一般臨床における乳腺専門医の育成はもちろん、臨床研究活動を通して、早くから乳腺腫瘍学の探求に携われるような機会を得るように工夫しています。大阪大学の関連施設であり、希望者は大阪大学医学系研究科乳腺内分泌外科(野口眞三郎教授)への入局ならびに大学院医学博士取得コースへの進学も可能です。
|
|
2.
|
研修計画
乳腺認定医・専門医カリキュラムでは、基本的領域診療科(外科、産婦人科、内科、放射線科のいづれか)の認定医または専門医であることがまず最初のステップになる。腫瘍学は従来から外科学とともに進歩してきた経緯もあり、全身疾患であることも鑑みると、基本的には外科専門医の修練を基盤としてつむことを期待する。日本外科学会専門医取得に関しては、当院外科研修プログラムに沿い、臨床研修医の2年と後期研修の3年で取得できるように工夫されているので、詳細は外科カリキュラムを参考にされたい。
乳腺認定医の条件には、その他に「継続4年以上学会会員であること」「臨床研修医終了後、本学会が認定した認定施設において所定の修練カリキュラムにしたがい通算2年以上の修練を行っていること。ただし、平成15年迄の医師免許取得者は、医師免許取得後4年以上修練し、そのうち2年以上は認定施設において所定の修練カリキュラムに従い修練を行っていること」「乳腺疾患に関する業績を有すること」が必須である。
また、専門医の取得条件については、「継続5年以上学会会員であること」「臨床研修医終了後、認定施設において所定の修練カリキュラムにしたがい通算5年以上の修練を行っていること。ただし、平成15年迄の医師免許取得者は、医師免許取得後7年以上修練し、そのうち5年以上は認定施設において所定の修練カリキュラムに従い修練を行っていること」がある。逆に、解釈すると、認定医には最速で卒後5年(外科専門医と同時期に取得も可能)、専門医には卒後7年で取得可能であることから、乳腺専門医を志す先生には、外科後期研修の3年の期間に、乳腺研究カリキュラムを前倒しして行うことにより、早い時期での取得ができる(図参照)。各自の目標の応じて、大阪医療センターでは、後期専修医3年および5年コースを選択できる。
また、乳腺臨床は、外科学一般のみならず、放射線診断学、病理学、放射線治療学などの横断的知識と経験の修練ならびに看護師・薬剤師などの医療スタッフとの「チーム医療」の実践が不可欠であることより、それらの部門との協調のもと、研修プログラムを実践する。
詳細は別添付表を参考にされたいが、当院における初期認定医取得目標と専門医取得目標を各年毎に記す。
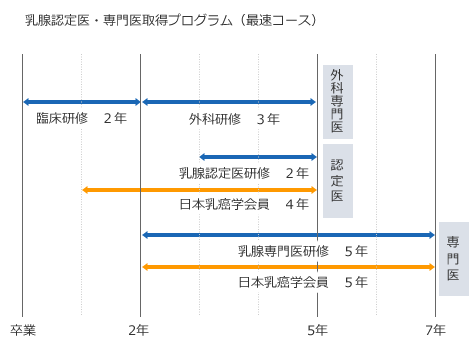
|
| |
(A)認定医研修期間(2年)
<1年目>
- 乳腺疾患症例の受持ちを担当し、その基礎的知識の習得をめざす。解剖・生理・病理
- 診療の補助を行い、基本的な診療の流れ、各検査の意義、超音波検査や処置の手技を習得する
- 手術では主に第1もしくは第2助手の経験をつむ
- 術前術後管理および患者指導が責任をもって行う
- 乳腺カンファレンスに参加し、担当症例のプレゼンテーションができる
<2年目>
- 乳腺疾患症例の受持ちを通し、画像診断(マンモグラフィ・エコー・MRIやCTなど)ができ、手術方法の最適な方法を提示できる
- 手術では指導医の監督の元、術者としての経験をつむ。術前および術後の患者へのICを行える。
- 病理診断を理解でき、術後の治療方針(薬物療法・放射線療法など)を提示できる
- 術前および術後の患者へのICを行ることができる
- 乳がんの疫学・検診への理解を深める
- 基本的な乳腺良性疾患の理解と経験をつむ
- 薬物療法患者のマネージメントができる。最新のEBMを検索し、その結果を臨床応用できる。臨床試験への参画から、その意義と治験に関しても興味をもつ
- 症例報告を中心に学術集会での発表を行う
(B)専門医研修期間(5年)
<1年目>
- 1. 乳腺疾患症例の受持ちを担当。臨床および画像診断から、治療方針の決定を提示できる
- 手術では指導医の監督の元、術者としての経験をつむ
- 病理診断を理解でき、術後の治療方針(薬物療法・放射線療法など)を決定できる
- EBMおよび患者希望に応じたICを提供できる
- 外来では、受持ち患者の術後経過観察、薬物療法の担当医として、マネージメントできる
- 症例報告を中心に学術集会での発表を行うと同時に論文を仕上げる
<2年目>
- 乳腺疾患症例の受持ちを担当。臨床および画像診断から、治療方針を決定できる
- 手術では指導医の監督の元、術者としての経験をつむと同時に後輩の指導を経験する
- 病理診断を理解でき、術後の治療方針(薬物療法・放射線療法など)を決定できる。
- EBMおよび患者希望に応じたICを提供できる
- 外来では、初診患者の診療に責任を持って従事する。画像ガイド下インターベンション診断も実施できる
- 再発症例の治療を担当し、長期の治療プランを立てることができる。各患者の社会的背景に合わせた、緩和・終末期医療の実践を、チームの一員としてその役割を担う。
- チーム医療を理解し、その中心的役割を担う
- 臨床テーマを中心に学術集会での発表を行うと同時に論文を仕上げる。
<3年目>
- 乳癌症例の、診断⇒治療⇒経過観察の一連に、責任を持って担当できる(コーディネーター的役割)
- 後輩に指導的立場として、各診療の場面で、アドバイスができる
- 常に、トラブル対策が事前に準備できた状況で診療にあたり、トラブル回避の術を習得している
- マンモグラフィ読影の資格を取得する(精中委のA判定)
- エコー検査で責任を持って診断を行う
- 良性疾患の理解とそのマネージメントができる
- 臨床試験・治験の患者を担当し、CRFの記載や、それにまつわる法規的事項の理解も深める
- 社会的役割(検診への協力、市民への啓発など)を担うことができる
<4年目>
- 乳癌症例の統括的マネージメントができ、乳腺カンファレンスで総合司会を行う
- 研修医の指導・監督ができる
- 基本的な病理診断ができる(組織型、異型度などの評価)
- 臨床テーマを中心に学術活動(発表と論文)。学会では討論に参加し、自らの意見をのべることができる
- 各種研究会・学会活動に積極的に参加し、常に医学の進歩にあわせた自己研鑽を行う術を習得する
- セカンドオピニオンに適切な説明ができる
- 稀な疾患(肉腫・リンパ腫など)や特殊な良性疾患の治療(乳輪下膿瘍・産褥乳腺炎など)の的確な治療方針を立てることができる
<5年目>
- 診断・治療において、指導者としての任務を遂行する
- 乳腺グループの各職種(チームワーク医療)との折衝やマネージメントができる
- 病院経営にも理解を深め、医療経済的側面から、乳腺臨床の抱える問題点を解決できる
- 自主研究(臨床試験)を計画し、遂行できる。
- 検診業務への参画(読影医・住民啓発・行政や医師会との折衝・システム精度管理など)
- 治験分担医師としての経験を積む
- 学術活動(発表と論文)を行うとともに、後輩の指導・育成ができる。
- 国際学会への参加を通し、世界的観知からわが国の情勢を理解できる。
- 社会的活動(住民啓発・病診連携・地域学術講演会など)を企画できる。
|
| 3. |
指導体制
外科科長である関本貢嗣が、全般に指導責任者となる。増田慎三(平成5年卒)、山村順(平成9年卒)が乳癌学会専門医として指導医である。増田慎三は大阪大学医学系研究科乳腺内分泌外科の臨床准教授も兼任し、医学生の実地臨床研修の指導も担当する。
外科は疾患毎に専任スタッフ制をとり、初期研修医ならび専修医の指導を担当する。水谷麻紀子(平成15年卒)、八十島宏行(平成15年卒)も加わり、乳腺専任スタッフは4名である。
現在、外科においては常時9-12名の専修医が勤務している。専修医は前期研修医と同様に入院患者の担当医となるが、外科専門医を標傍するための専門教育を受けている。また、病棟病務や患者管理の実務においては、研修医の直接指導を担当し、その術も習得する。
乳腺疾患領域では、特に関係の深い他診療科として、病理部門(真能正幸・児玉良典)、放射線診断(栗山啓子・金澤達)、放射線治療(田中英一)、形成外科(吉龍澄子)などからも乳腺疾患の専門医として指導を得る。
|
| 4. |
研修カリキュラム到達目標
1.認定医取得のための細則を表1と表2に示す。乳癌学会HPより抜粋。
表1;乳腺認定医が理解しなければならない基礎的事項
|
項 目
|
理解度
|
|
解剖
|
(正常乳房の基本的な組織像、乳房腋窩領域の解剖)
|
|
|
生 理
(性ホルモン
と乳腺)
|
性周期と乳腺
|
|
|
妊娠・授乳期乳腺
|
|
|
加齢による乳腺の変化
|
|
|
その他(食事,肥満,HRT など)
|
|
|
疫 学
|
一般的事項(罹患率、死亡率、再発形式)
|
|
|
家族性乳癌
|
|
|
危険因子
|
|
|
その他( )
|
|
|
病 理
|
先天異常と発達異常
|
|
|
良性疾患
|
炎症
|
|
|
乳腺症
|
|
|
乳管内乳頭腫
|
|
|
乳頭部腺腫
|
|
|
腺腫
|
|
|
線維腺腫
|
|
|
葉状腫瘍
|
|
|
乳管拡張症
|
|
|
炎症性偽腫瘍
|
|
|
女性化乳房症
|
|
|
その他( )
|
|
|
悪性疾患
|
非浸潤性乳管癌
|
|
|
非浸潤性小葉癌
|
|
|
乳頭腺管癌
|
|
|
充実腺管癌
|
|
|
硬癌
|
|
|
特殊型
|
|
|
Paget病
|
|
|
炎症性乳癌
|
|
|
男子乳癌
|
|
|
妊娠・授乳期乳癌
|
|
|
非上皮性腫瘍
|
|
|
病理組織悪性度の分類
|
|
|
その他( )
|
|
|
バイオロジー
|
自然史
|
|
|
増殖・進展
|
|
|
ヘテロジェナイティ
|
|
|
ホルモンレセプター
|
|
|
癌関連遺伝子
|
|
|
その他( )
|
|
|
検 診
|
集団検診
|
|
|
自己検診
|
|
|
診 断
|
間診と病歴の取りかた
|
|
|
視触診
|
|
|
病期分類
|
|
|
乳房画像診断(マンモクラフィ,超音波診断,サ一モグラフィ,CT,MRI)
|
|
|
骨シンチグラフィ
|
|
|
CT(乳房外)
|
|
|
MRI (乳房外)
|
|
|
超音波診断(乳房外)
|
|
|
腫瘍マーカー
|
|
|
細胞診
|
|
|
針生検
|
|
|
外科的生検
|
|
|
その他( )
|
|
|
治 療
|
治療方針の適応決定
|
|
|
局所療法
|
手術
|
乳房切除術
|
|
|
乳房温存手術
|
|
|
リンパ節郭清
|
|
|
放射線療法
|
|
|
全身療法
|
化学療法
|
|
|
内分泌療法
|
|
|
その他( )
|
|
|
治療効果の判定方法
|
|
|
薬物有害反応
|
|
|
その他( )
|
|
|
リハビリテーション
|
|
|
緩和・終末期医療
|
|
|
医療倫理
|
インフォームドコンセント
|
|
|
クオリティオブライフ
|
|
|
カウンセリング
|
|
|
臨床試験
|
|
|
医療保障,医療経済
|
|
表2;乳腺認定医が経験しなければならない外科的事項
|
診療対象
|
A(件)
|
39以下
|
40~99
|
100以上
|
|
|
|
乳癌
|
□
|
□
|
□
|
|
|
|
|
10以下
|
11~50
|
51~100
|
101~200
|
201以上
|
|
|
乳腺症
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
|
線維腺腫
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
|
女性化乳房症
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
|
B(確認)
|
|
|
思春期早発症
|
□
|
|
|
|
巨大乳房
|
□
|
|
|
副乳
|
□
|
|
|
陥没乳頭
|
□
|
|
|
乳管拡張症
|
□
|
|
|
乳汁漏出症
|
□
|
|
|
周期性乳房痛(月経依存性)
|
□
|
|
|
急性乳腺炎
|
□
|
|
|
乳管内乳頭腫
|
□
|
|
|
乳頭部腺腫
|
□
|
|
|
腺腫
|
□
|
|
|
葉状腫瘍
|
□
|
|
|
Paget病
|
□
|
|
|
肉腫
|
□
|
|
|
その他( )
|
□
|
|
|
診 断
|
A(件)
|
10以下
|
11~20
|
21~50
|
51~100
|
101~200
|
201以上
|
|
マンモグラフィ(乳管造影法を含む)
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
超音波診断
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
サーモグラフィ
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
乳管内視鏡
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
細胞診
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
針生検
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
外科的生検
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
その他( )
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
治 療
|
A(件)
|
10以下
|
11~20
|
21~50
|
51~100
|
101~200
|
201以上
|
|
切開排膿術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
腫瘤摘出術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
乳房切除術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
乳房温存手術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
再発巣切除
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
内分泌療法
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
化学療法
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
乳房再建術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
乳房形成術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
卵巣摘出術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
植皮術
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
その他( )
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
□
|
|
医療倫理
|
B(確認)
|
|
臨床試験
|
□
|
|
|
医療相談(カウンセリング)
|
□
|
|
その他( )
|
□
|
|
| |
2.専門医取得のための細則目標を下記に示す。乳癌学会HPより抜粋。 |
|
|
■一般目標1
乳腺認定医としての医療技術、知識を基礎にし、さらに乳腺専門医として乳腺疾患の診療を実践できる医師を養成するための到達目標を定め、研修を実施する。認定施設における研修期間は、通算5年以上を必須とする。
1) 乳腺疾患全体を包括した専門医としての知識、臨床的判断能力、問題解決能力を習得する。
2) 各専門分野における診療を適切に遂行できる技術を習得する。
3) 医学、医療の進歩に合わせた生涯学習を行う方略、方法の基本を習得する。
4) 自らの研修とともに上記項目について後進の指導を行う能力を習得する。
■到達目標1(基礎的知識)
各専門分野の乳腺診療に共通して必要な下記の基本的知識を習熟し、臨床に即した対応ができる。
1) 解剖
正常乳房の組織像、乳房腋窩領域の解剖を理解している。
2) 乳腺の生理とホルモン環境
性周期と乳腺、妊娠・授乳期乳腺、加齢、肥満、ホルモン補充療法(HRT)、ピルなどによる
乳腺の変化に関する知識を習得している。
3) 疫学
乳癌の疫学に関する一般的事項(罹患率、死亡率、再発形式)、家族性乳癌、危険因子などに関する
最新のデータを認知している。
4) 病理
下記乳腺疾患のマクロ・ミクロの病理を理解し、画像診断との対比ができる。
(1) 先天異常と発達異常
(2) 良性疾患:炎症、乳腺症、乳管内乳頭腫、乳頭部腺腫、腺腫、線維腺腫、葉状腫瘍、
乳管拡張症、炎症性偽腫瘍、女性化乳房症、その他
(3) 悪性疾患:非浸潤性乳管癌、非浸潤性小葉癌、乳頭腺管癌、充実腺管癌、硬癌、
特殊型、
Paget病、炎症性乳癌、妊娠関連乳癌、非上皮性腫瘍、病理組織悪性度の分類、その他
5) バイオロジー
乳癌の自然史、増殖・進展、ヘテロジェナイティ、ホルモンレセプター、癌関連因子などの
バイオロジーに関する最新の知見を習得している。
6) 検診
(1) 世界および我が国における乳癌集団検診の考え方と現状を把握している。
(2) 乳癌の自己検診法を理解している。
■到達目標2(基本的診療技術)
乳腺疾患の診療に必要な知識、検査、処置に習熟し、EBMに基づいた診療を行うことができる。
A.診断
1) 問診・病歴・視触診
乳腺疾患患者の問診・視触診を行うことができる。
2) 病期分類
乳癌取扱い規約およびUICCによる乳癌の病期分類ができる。
3) 画像診断
(1) マンモグラフィ:画像評価および読影(カテゴリー分類など)ができる。
(2) 乳房超音波検査、乳管造影、MRマンモグラフィ、乳腺CT、胸部CT、上腹部CT、
腹部超音波検査、骨シンチグラフィ、頭部CT、頭部MRI、骨MRI:適応を決定し、
読影することができる。
(3) 上記画像診断の各種検査法の特性を理解して検査計画を作り、総合診断ができる。
4) 腫瘍マーカー:適応を決定し、検査結果を評価できる。
5) 擦過細胞診・穿刺吸引細胞診、針生検、吸引式組織生検(マンモトーム)、外科的生検:適応
を決定し、結果を理解することができる。
6) センチネルリンパ節生検の実施方法と意義を理解している。
B.治療
1) 乳腺の良性疾患および悪性疾患に対して問診・視触診・画像診断などの結果に基づいた
適切な治療方針を決定することができる。
2) 乳癌に対する外科治療、放射線治療、化学療法および内分泌療法の役割を理解し、
それぞれの適応を決定することができる。
3) 乳癌に対する緩和医療の内容を理解し、適応を決定することができる。
4) 乳癌根治術後リハビリテーションの意義を理解している。
C.医療倫理など
1) 最新のEBMを検索し、その結果を臨床応用できる。
2) 患者側に診療方針選択の権利があることを理解し、適切なインフォームド・コンセントを得ることができる。
3) セカンドオピニオンを求めてきた症例に対し適切な説明を行うことができる。
4) 臨床試験の意義を理解し、参加することができる。
■到達目標3(専門的診療技術)
行動目標
下記の各専門分野別に乳腺疾患の診療内容を理解し、EBMに基づいた医療を実施できる能力を習得し、臨床応用できる。(外科の内容のみ記載)
<外科>
担当医として乳腺外科に包含される主要な疾患に対する診断と治療をもれなく経験することを必要とする。
1) 診療対象:下記の乳腺疾患の定められた症例数以上の診療経験を必要とする。
(1) 乳癌100例
(2) 乳腺症30例、線維腺腫20例、女性化乳房症5例
(3) 思春期早発症、副乳、乳管拡張症、乳汁漏出症、周期性乳房痛(月経依存性)、乳瘤、
急性乳腺炎、産褥乳腺炎、乳輪下膿瘍、乳管内乳頭腫、乳頭部腺腫、腺腫、葉状腫瘍、
Paget病、肉腫:これらの疾患について合計20例
2) 診断:下記の検査について定められた件数以上の診療経験を必要とする。
このうち、1つの項目について200例以上の経験を有しなければならない。
(1) マンモグラフィ:読影経験100例
(2) 乳房超音波検査:読影経験100例
(3) MRマンモグラフィまたは乳腺CT検査:読影経験30例
(4) 穿刺吸引細胞診:実施経験20例
(5) 針生検(または吸引式組織生検):実施経験10例
3) 治療:下記の治療法について定められた件数以上の経験を必要とする。このうち、乳房切除術、
乳房温存手術などの乳癌手術は、術者または指導者として100例以上経験しなければならない。
(1) 乳房切除術30例、乳房温存術30例
(2) 切開排膿術、腫瘤摘出術、再発巣切除術の合計20例
(3) 内分泌療法30例
(4) 化学療法30例
(5) 乳癌根治術が必要な患者を担当し、術前評価、術前管理、インフォームド・コンセント、
術後管理ができる。
(6) 乳癌術後リハビリテーションの患者への指導ができる。
(7) 乳癌に対する術前化学療法の適応を決定し、実施することができる。
(8) 乳癌術後の補助療法の適応を決定することができる。
(9) 乳癌術後の適切なフォロー・アップができる。
■到達目標4(生涯教育)
乳腺疾患診療の進歩に合わせた生涯教育を行う方略、方法の基本を習得する。
1)施設内の病理を含む各専門領域が集まる乳腺カンファレンスに出席し、それぞれの専
門的立場から意見を述べることができる。
2)施設内乳腺カンファレンスを司会し、積極的に討論に参加する。
3)最新のEBMを検索する能力を有し、個々の症例に合わせてEBMに基づいた診療を
行う。
4)学術集会、教育集会に参加し、日進月歩の医学、医療の実情に触れる。
5)学術集会、学術出版物に症例報告や臨床研究の結果を発表する。
■到達目標5(医療行政)
医療行政、病院管理(リスクマネージメント、医療経営、チーム医療など)についての重要性を理解し、実地医療現場で実行する能力を習得する。
|
| 5: |
乳腺グループの週間予定表(2012年8月現在)
| 月: |
8:00~9:00 |
外科総合術前カンファレンス |
| |
9:00~17:30 |
外来 2診察・手術AM/PM 2単位 |
| |
17:30~19:30 |
乳腺カンファレンス(術前術後、病理診断、治療方針決定) |
| 火: |
830~9:00 |
乳腺病棟回診と症例検討 |
| |
9:00~17:30 |
外来 5診察 |
| 水: |
8:30~17:30 |
外来 1診察・手術AM/PM 2単位 |
| |
17:00~18:00 |
外科総合病棟回診と外科抄読会 |
| 木: |
8:30~17:30 |
外来 2診察・手術AM 1単位 |
| |
15:30~16:00 |
乳腺病棟カンファレンス(入院患者を中心に) |
| |
16:00~17:00 |
乳腺病棟回診と症例検討 |
| 金: |
8:30~17:30 |
外来 2診察・手術AM 1単位 |
★基本的な一般外科修練を終えた後(外科専門医取得めどが立った段階で)、乳腺専門コースに入れば、乳腺専門外来の担当、ならびに週1-2単位の病理診断研修をはじめ、希望に応じて他科専門医の直接指導研修のプランも考慮可能である。また将来的には国内関連施設間での他施設交流研修も計画中である。
|
| 6: |
診療実績など
年間症例数 原発性乳癌 200-235例
乳房温存率 約70%、センチネルリンパ節生検実施
術前薬物療法実施率 約30%
乳腺関連臨床試験(開発治験含む)実施件数 約50件
セカンドオピニオン外来
日本乳癌学会認定施設
マンモグラフィ精度管理中央委員会認定施設
日本臨床腫瘍学会認定施設
高度先進医療実施施設 など
<臨床試験参加グループ>
JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)
JBCRG (Japan Breast Cancer Research Group)
CSPOR(乳癌患者のQALY向上のための治療法開発支援事業)
KBCSG-TR(近畿乳癌研究グループ)
WJOG(西日本がん臨床研究グループ)
KMBOG(Kinki Multidisplenary Breast Oncology Group:事務局) など |