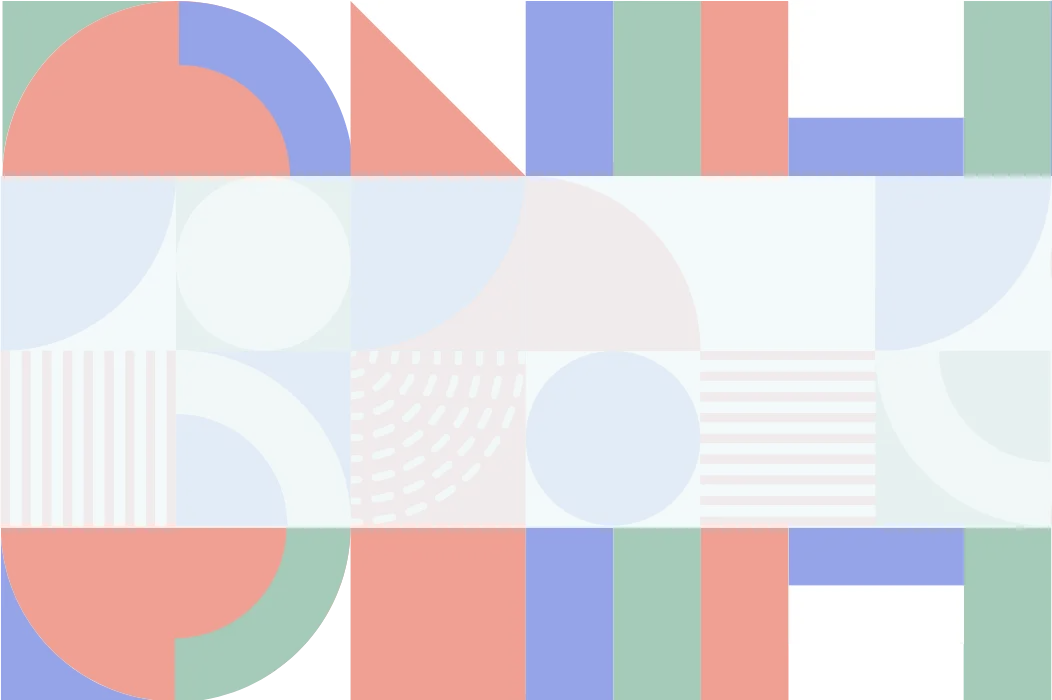| 1. |
診療科(専門領域)
小児科 |
|
2.
|
コースの概要
日本小児科学会は「小児科医の到達目標」において、小児科医の役割を「小児科医は成長期にある小児の健康上の問題点を全人的に、かつ家族、地域社会の一員として把握する。その扱う疾患は、一般の急性・慢性の疾患、新生児固有の疾患、先天性あるいは遺伝性の疾患及び身体諸機能の障害、心因性疾患、行動発達の異常である。また、小児の健康保持とその増進及び疾病・障害の早期発見とそれらの予防の役割を担う」としている。当院は日本小児科学会専門医制度研修施設であり、日本小児科学会の方針に沿って、後期臨床研修を行う。
具体的には3年間の後期臨床研修の間に、「小児科専門医の教育目標」に基づく研修内容を経験することになる。
後期臨床研修の間は病棟主治医として患者を受け持ち、基本的・専門的な疾患の診療を行う。また外来においても退院患者の経過観察を行い、一般外来の診療も受け持つ。時間外診療も分担して経験することで、救急医療についても研修する。 当院小児科は以前から血液疾患(急性白血病、血友病など)の診療に力を入れてきた。また病院の立地などの影響から、いわゆる急性疾患は比較的少なく、慢性疾患や専門性の高い疾患の比率が高い。スタッフの専門も多岐にわたっており、小児科の各分野の疾患を幅広く経験することができる。 |
| 3. |
取得資格
国立病院機構における診療認定医(I)資格
小児科専門医(日本小児科学会)の取得資格 |
| 4. |
長期目標
日本小児科学会「小児科専門医の教育目標」が到達目標となる。
|
| 5. |
取得手技
日本小児科学会「小児科専門医の教育目標」に示されている手技を取得することができる。 |
| 6. |
研修期間
3年 |
| 7. |
募集人数
2名 |
| 8. |
診療科の実績と経験目標症例数
症例数と手技件数の調査年度 |
| |
|
主要疾患
|
入院数(年間)
|
経験目標症例数( 3 年間)
|
|
急性白血病
|
15
|
10
|
|
血友病・紫斑病
|
10
|
10
|
|
その他の血液疾患
|
5
|
5
|
|
膠原病・川崎病・不明熱
|
15
|
10
|
|
気管支喘息
|
15
|
10
|
|
気道感染症
|
80
|
40
|
|
消化管感染症・消化器疾患
|
25
|
20
|
|
その他の感染症
|
15
|
15
|
|
神経疾患
|
5
|
10
|
|
内分泌疾患
|
5
|
10
|
|
腎疾患
|
5
|
10
|
|
低出生体重児
|
50
|
30
|
|
その他の新生児疾患
|
80
|
50
|
|
| |
|
手技
|
件数(年間)
|
経験目標件数( 3 年間)
|
|
骨髄穿刺
|
30
|
30
|
|
腰椎穿刺
|
30
|
30
|
|
| 9. |
診療科の指導体制
診療科医師数:常勤 4 名
診療科研修の指導にあたる医師:4名
主として研修指導にあたる医師の氏名:多和 昭雄
主として研修指導にあたる医師の診療科経験年数:36年 |
| 10. |
コンセプト
研修に際しては医師としての社会的、職業的責任と医の倫理に立脚してその職務を遂行し、幼い患児の人格と人権を尊重し、家族とも好ましい信頼関係を作り、説明と同意を基本的態度として接することが肝要である。特に致死的あるいは永続的障害や慢性疾患を有する患児については真摯な態度で接し、家族を含めた心理的援助を行うことができる小児科医を目指してほしい。また、受け身の研修でなく常に積極的に自己研鑽に努め、種々の医療・医学情報を取り入れて、新しい知識の吸収に努める研修態度を期待する。 |
| 11. |
一般目標
・医療安全、患者への人権の配慮ができる。
・関連領域を含む幅広い知識で患者の病態の全貌を把握する。
・関連診療科と必要な協議をして、的確な治療計画を立案する。
・他の職種との意思疎通を図り、チーム医療を実践する。
・医学の進歩に伴う生涯学習を実践する。 |
| 12. |
関連領域の研修に関して
施設内での研修:可能
施設外との交流研修:可能
研修領域の決定:研修責任者が本人と相談の上決定
|
| 13. |
共通領域研修について |