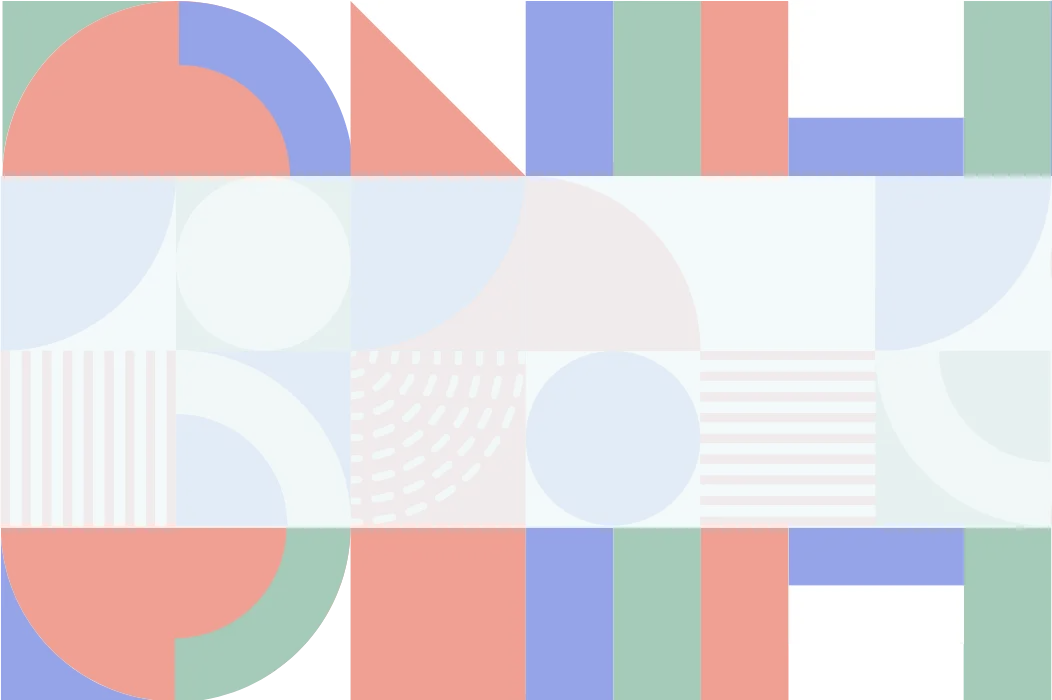胃がん(外科)胃がん(内科)
胃がん(外科)
- 1.解剖
- 2.胃がんとは
- 3.頻度
- 4.症状
- 5.検査と診断
- 6.進行度・病期
- 7.治療ガイドラインについて
- 8.治療
- 9.治療経過
- 10.治療成績
- 11.手術後の障害・後遺症
- 12.術後のフォローアップ
- 13.予防と検診
1.解剖
胃は食道につづいて上腹部ほぼ中央に位置し、条件により形はいろいろ変わります。また、胃の入り口から出口にかけて、噴門、胃体部、胃角部、幽門部とよびます。
2.胃がんとは
胃の粘膜から発生する上皮性の悪性腫瘍のこと。がんの深達度(深さ)から、早期がんと進行がんとに分けられます。
3.頻度
依然として我が国では頻度の高いがんですが、近年、やや減少傾向にあります。平成11年のがんによる死亡統計を部位別にみると、男性では肺がんに次いで胃がんが多い(肺がんはがん死亡全体の21.6%、胃がんは18.7%)。また、女性では胃がんが最も多く、15.6%を占めます。胃がんにかかる罹患率をみると、性別では男性に多く男女比は約2:1です。15歳から高齢まで幅広く発生しており、平成8年統計での胃がん罹患率は、人口10万人に対し男性は93.6人、女性では36.9人でした。
4.症状
早期がんではほとんど無症状で、検診での内視鏡やバリウムを使ったレントゲン検査で発見されることがほとんどです。進行がんの場合、体重減少、上腹部痛、吐下血、嘔吐、食事通過障害などの自覚症状以外に、上腹部腫瘤や転移リンパ節(首のつけねなど)を触ったり、そしてがんの進行度が増すにつれて、独特の口臭や全身の色素沈着などの所見を呈することがあります。
5.検査と診断
レントゲン検査-胃のなかにバリウムと空気をいれて充満させて撮影する二重造影法が主流です。この検査によってがんの大きさ、形、胃の壁の伸展性や可動性などの情報も得られ、進行程度の推測ができます。胃内視鏡および生検検査-胃の粘膜面を直接観察できるため、レントゲン検査での二重造影法とともに、またはそれ以上に、早期がんの診断に威力を発揮します。内視鏡検査で異常を発見すれば、組織片を採取して組織学的検索を行い、これを生検といいます。生検での組織学的診断は、Group I(正常胃粘膜)からGroup V(悪性)までの5段階で悪性度を評価します。腹部超音波検査、CT、超音波内視鏡-胃がんの肺や肝臓への転移、リンパ節への転移、胃の周囲の臓器への浸潤の程度や有無を腹部超音波検査やCTで詳しく診断します。また、内視鏡の先から超音波検査ができる超音波内視鏡検査を使って、がんの深さや胃の周囲へのリンパ節転移の有無なども診断できます。以上の検査で総合的に胃がんの診断を行い、最適な治療方針を決定します。
6.進行度・病期
がんの深達度(深さ)、リンパ管を介したリンパ節転移、血管を介した肝臓や肺への臓器転移、がんが胃の壁を突き破りお腹の中に散布される腹膜播種性転移の有無などにより胃がんの進行度(ステージ)を詳しく分類し、それぞれの進行度にあった治療法が決定されます。ちなみに、進行度が悪化するにつれてステージはIからIVまでの4段階に分けられます。
7.治療ガイドラインについて
1)胃癌の治療法についての適正な適応を示すこと
2)胃癌治療における病院間差を少なくすること
3)治療の安全性と治療成績の向上を図ること
4)無駄な治療を廃して、人的、経済的負担を軽減すること
5)ガイドラインを広く一般にも公開して、医療者と患者の相互理解にも役立てること
を目的として、平成13年3月に日本胃癌学会から「胃癌治療ガイドライン」が発表されました。次項にも示しているように、このガイドラインによって、それぞれの進行度にあった治療法が決定されます。当科も基本的にこれに従った治療方針をとっております。
8.治療
現在、胃がんを治癒させるためには切除が第一選択であり、主流を占めています。
抗癌剤を用いた化学療法、免疫療法、放射線療法その他を組み合わせた集学的治療も、進行や再発胃がんに行われています。
それぞれの進行度に対する切除方法を具体的に挙げると、内視鏡的粘膜切除術、縮小手術、定型手術、拡大手術、姑息手術(根治的な手術が望めない晩期症例に対し、出血や狭窄などの切迫した症状の改善を目的とした単切除やバイパス術のこと)などがあります。
当科では、科学的証拠にのっとって、縮小手術から拡大手術までの手術適応をきっちりと決め、それに従って積極的に治療を行っております。
手術適応のない進行や再発胃がんにたいしJCOG、OGSG、N-SASなどの臨床研究グループに積極的に参加し、延命効果を指標とした臨床研究を推進しております。
9.治療過程
当科での胃がんに対する外科手術治療過程の概略(クリニカル・パスの紹介):表を参照。
また、当科では基本的には、すべて病名を告知する方針です。つまり、この告知によって、ご自分の病気をしっかり理解してもらい、治療へ協力してもらうためです。
10.治療成績
当科も全国的にも、治療後の成績は同じです。平成元年から平成5年までの症例の術後5年生存率をみると、比較的早期がん症例であるステージIでは約90%、ステージII、III、IV各々で約76、47、13%です。
11.手術後の障害・後遺症
手術後早期合併症として、出血、縫合不全(胃と腸などをつないだ部分がしっかりつかないこと)、吻合部狭窄(つないだ部分が一時的な浮腫みにより狭くなること)などがあげられます。また、胃手術後の後遺症として、ダンピング症候群(胃の貯留機能が消失あるいは低下し、自律神経機能のアンバランスも加わりいろいろな症状がでる)、スターシス症候群(胃とつなげるために持ち上げた腸が動かない)、逆流性食道炎(胃の入り口の逆流防止機能がなくなるため、腸液が食道に逆流する)、お腹のなかの癒着による腸閉塞などがあげられます。
12.術後のフォローアップ
退院後2週間後に一度、その後1ヵ月から3ヵ月に一度の割合で外来受診してもらいます。外来での主な診療目的は、術後再発(転移など)と食事摂取状況などのQOL(生活の質)のチェックです。各患者さんの進行度にあわせて外来受診の頻度も異なりますが、術後5年間は少なくとも半年に一度は受診してもらうようにしています。
13.予防と検診
胃がんの成因に関しては明らかではないが、食習慣の関与が示唆されています。また近年、ヘリコバクタ-・ピロリ菌の感染と胃がん発生との因果関係も報告されています。
胃がん(内科)
1.解説
食物は、のどから食道を通過し胃に入ります。食物は、胃に入ると胃液と混ざり、消化されて、適量ずつ十二指腸へ送り出されます。胃液は、食物が胃に入ってくると分泌されますが、ほとんどが塩酸で、強い酸による殺菌作用と食物を粥状にする作用を持ちます。
解剖学的には、胃は、食道からの入口部分である噴門部、胃の中心部分である体部、十二指腸側への出口部分の幽門部に大きく分けられます。胃の入口付近の胃体部と呼ばれる部分は胃酸や内因子を分泌し、胃の出口に近い部分は食べ物を送り出すポンプの役割をします。また、胃の壁は、最内層が胃液や粘液を分泌する粘膜、その下が胃の動きを担当する筋層、最外層は臓器全体を包む薄い膜で漿膜と呼ばれます。
さて、胃がんは、粘膜内の分泌細胞や、分泌物を胃の中に導く導管の細胞から発生します。胃壁の外に向かって粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜へと徐々に深く浸潤をはじめると、それに伴って転移しやすくなり、予後が悪くなってきます。このがんの外方向への進展は深達度と呼ばれています。
また、胃の前がん状態として慢性萎縮性胃炎があり、塩分の取りすぎやヘリコバクター・ピロリと呼ばれる細菌の胃内での感染により起こります。たばこが胃がんを増やすともされています。逆に、ビタミンCやカロチノイド類を多く含む生野菜や果物を多く食べる方に胃がんが少ないことがわかってきました。
2.症状
早期胃がんでは、全く症状がないことも多いのですが、病変の中に潰瘍ができると、痛み、出血、胃部不快感などが出現します。進行したがんの症状は、食事が通らない、胃が重い、体重が減る、食べ物がつかえるなどのものです。貧血のために動悸や息切れが生じることもあります。
3.検査と診断
胃がんの検査は、主として胃X線・胃内視鏡検査ですが、これに加え、検診として血中ペプシノーゲン値、腫瘍マーカーの測定や、精密検査として腹部超音波、CTなどが行われます。
1)胃X線検査
X線を透過しないバリウムという物質(造影剤)と、胃をふくらませるために発泡剤を飲み、空気とバリウムで胃内の微細な凹凸や形態的変化を映し出します。内視鏡に較べ、胃の形態や粘膜表面の異常のみならず、胃壁の動きや進展性の異常などもとらえることができ、がんの存在、がんの浸潤範囲、壁の深達度などの診断にも用います。
2)内視鏡検査
径約1cmのファイバースコープを口から挿入し、胃内に光ファイバーを通して光を送って直接胃の中を観察し、画像を写真に記録します。また、組織生検といって、胃の粘膜の一部を採取し、顕微鏡によりがんの診断を行います。がんの診断は最終的には組織生検によりなされるため、がんの診断の確定にはどうしても内視鏡検査が必要です。このように、がんの存在の確定診断、がんの拡がり・深さの診断を行います。
3)CT
X線を用いて腹部や胸部の臓器の輪切りの像を描き出し、胃がんの肝臓・リンパ節への転移、周辺臓器への浸潤などを調べます。がんの病期分類と治療法決定に必要です。
4.進行度・病期
胃がんの病期(ステージ)分類は、深達度、リンパ節転移、他の臓器の転移により決定されます。
早期胃がんは、深さが粘膜下層までの浸潤にとどまっているがんをいい、それより深い固有筋層に達するものは進行癌と分類されます。がんの深さと転移の程度はよく相関しており治療方針の決定にも重要です。胃がんで最も多い転移のリンパ節転移は、早期/進行がんの分類には関係せず、早期がんでもリンパ節転移例は少ないながら含まれます。早期がんでも、粘膜内にとどまるものと粘膜下層まで達するものでは、リンパ節転移の率は各3%、15-20%とかなり違い、内視鏡治療適応の分かれ目になります。リンパ節転移の次に腹膜転移と肝転移が多く、前者は、胃壁の最外層に到達したがん細胞が壁から飛び散り、腹腔内で増殖します。腹膜播種とも呼ばれ、腹水や腸の狭窄を引き起こします。後者は胃の静脈内に入り込んだがん細胞が肝臓に転移病巣を形成するものです。これらの転移がある場合は、外科療法ではとりきれず、IV期として、手術可能なIII期までと区別されます。
5.治療
1)切除療法
切除の範囲はがんの部位、進みぐあいから決定されます。開腹下手術や局所治療として内視鏡治療が行われています。リンパ節へ転移している可能性がほとんどないがんでは、リンパ節郭清が不要と考えられ、内視鏡による胃粘膜だけの切除や腹腔鏡下に胃のごく一部だけを切除する方法がとられます。リンパ節転移の可能性がある程度高いがんでは、リンパ節郭清が必要で、開腹科の手術が必要です。このうち、がんの部位が噴門に近い場合、またはがんが噴門近くまで這ってきている場合は胃全摘、がんの位置が噴門と離れていれば幽門側胃切除が行われます。後者の場合、胃の入口の噴門は温存され、胃の2/3から4/5程度が切除されます。
他に、治療決定の際には、手術の危険性や基礎疾患、予想される治療予後などが考慮されます。手術自体での死亡率は胃全摘術でおよそ1%、幽門側胃切除で0.2%で、さらに余病があれば手術の危険性はより高くなります。また、病期別の治療例の5年生存率は、Ia:92%、Ib:90%、II:76%、IIIa:59%、IIIb:37%、IV:8%とされ、高齢者では年齢別平均余命と期待生存期間を比べ治療を決定する場合もあります。
2)内視鏡的治療
内視鏡的治療は、胃の内腔の表層だけをはぎ取るという局所切除のため、リンパ節転移の可能性のほぼない癌に行われます。リンパ節転移の有無は、経験的に、手術切除標本より組織型・深達度・形状(病巣内潰瘍有無も含む)・大きさの組み合わせにより類推されます。すなわち、早期胃がんのうち、一般には、粘膜内の分化型腺癌かつ、隆起型は2cm以内、陥凹型は病巣内潰瘍がない1cm以内のがんが対象となっています。最近の内視鏡技術の発達によりこの適応は徐々に拡大されています。
内視鏡的胃粘膜切除術の方法は、内視鏡下で、病巣粘膜の下に生理食塩水などを注入して病変の粘膜を浮き上がらせ、輪状の針金で粘膜を電気で焼き切る方法です。切除された病変を検索し、病変のどこにもリンパ管や静脈への浸潤がないこと、粘膜下層への浸潤がないこと、切り口にがんがなく完全に切除していることを顕微鏡的に確認します。内視鏡治療は、他にレーザー治療や光化学療法がありますが、切除組織の確認が出来ないため、胃粘膜切除術が主として行われています。合併症としては、出血と穿孔がありますが、ほとんどは内視鏡的に対処できるとされています。
EMR後再発症例の特徴と再治療
(全国の代表的な10施設の集計結果より)
| EMR総数 | 3087例 |
| 再発症例 | 366例(11.9%)、施設間の変動幅 4.2-22.3% |
| 再発症例の規約上の完全例 | 17/1443(1.26%)施設間の変動幅 0-4% |
| 不完全切除例 | 295/996(29.6%)施設間の変動幅 10-39.3% |
| 再発までの期間 | 366例 |
| 3ヶ月以内 | 167例(47.3%) |
| 6ヶ月以内 | 69例(18.8%) |
| 12ヶ月以内 | 69例(18.8%) |
| 1年以上 | 61例(16.7%) |
| 再発例の癌深達度 | 366例 |
| m | 331例(90.4%) |
| sm | 35例(9.6%) |
| 再発の治療 | 366例 |
| EMR再施行 | 173例(47.3%) |
| レーザー焼灼 | 37例(10.1%) |
| 腹腔鏡下手術 | 19例(5.2%) |
| 開腹胃切除 | 88例(24.0%) |
| その他 | 49例(13.4%) |
3)化学療法
切除不能がんや再発がんの場合や術前・術後の補助療法として、化学療法が行われます。
従来化学療法は有効率が20―30%で、副作用なども考えると、成績がいまひとつでしたが、最近、有望な薬剤が開発されたり、50%位の有効率を認めた抗癌剤の新しい組み合わせが出てきています。具体的には、フルオロウラシル、シスプラチン、アドリアマイシン、イリノテカンや、経口抗がん剤のテガフール・ギメスタット・オタスタットカリウム(S1: エスワン)などの組み合わせが有望視され、治験が行われています。
副作用として、がん細胞にだけ選択的に効く薬はなく、抗がん剤は身体の中で新陳代謝の盛んな細胞も同時に壊してしまうため、副作用は避けられません。頭髪、消化管粘膜、骨髄などに作用し、脱毛、口内炎、下痢、吐き気、白血球や血小板の減少がおこります。それ以外には、心臓に対する直接作用があったり、薬剤の代謝や排泄で重要な肝臓や腎臓に障害をおこすこともあります。
補助化学療法としては、術前には切除しきれない腫瘍を縮小あるいは消失させることによって、残存する腫瘍を外科的に切除する方法も行われています。手術後の再発予防の目的で行われる補助化学療法は、残念ながらその効果もはっきりしていません。