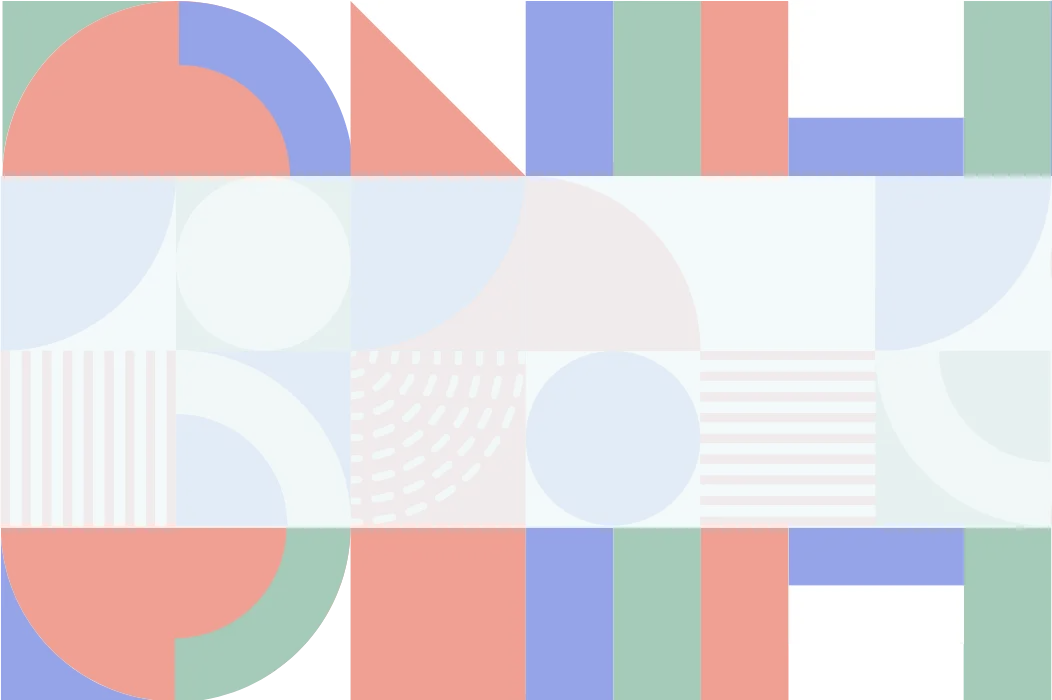精巣腫瘍(泌尿器科)
1.概説
精巣は「睾丸」の方がなじみのある名称であるが、男性の陰嚢内に左右各1個あり、卵型をしており、通称「タマ」と呼ばれているものである。男性ホルモンおよび精子を産生している。
2.頻度
精巣腫瘍は日本人男性10万人当たり1~2人と頻度は極めて低く、われわれも年間数例を経験するに過ぎないが、好発年齢は0~10歳、20~40歳、60歳以上の3峰性であり、生下時や20~40歳の男性で最も多い腫瘍であるため、社会的には極めて重要な疾患の一つである。
精巣腫瘍の罹患率は国別や人種差が大きく、スカンジナビア(デンマーク、ノルウェー)やスイス、ドイツ、ニュージーランドで最も頻度が高く、米国や英国は中間、アフリカやアジアでは頻度が低い。
また、米国の黒人は白人の約1/3の頻度であるが、アフリカの黒人と比較すると約10倍の頻度である。
ハワイでのフィリピン人・日本人は中国人・白人・現地ハワイ人の約1/10の頻度である。
3.危険因子
精巣腫瘍になりやすいものとしては、停留精巣、精巣外傷、妊娠時のホルモン剤投与、萎縮精巣などが考えられているが、外傷については関係が薄いとされている。
停留精巣(精巣が陰嚢内に降りずに鼠径部や腹腔内に留まっている病態)が精巣腫瘍を生じる危険率については、正常人の数倍とするものから200倍とするものまで様々な報告があるが、最近では3~14倍の危険率であるとされ、精巣固定術により精巣を陰嚢内に降ろしても、その危険率は変わらないとされている。
また、精巣腫瘍患者における両側(同時性、異時性を含む)の罹患率は2~3%であり、両側共に同一の組織型である場合が多い。
それ故、精巣腫瘍に罹患した人は、残る反対側の精巣に腫瘍が発生する可能性は通常の人よりも高い。
精巣腫瘍と遺伝要因との関係については、Harvald and Hauge(1963年)が7000組の双子を調査した結果、必ずしも高頻度ではなかったと報告しているが、Nicholson and Harland(1995年)は精巣腫瘍患者の1/3が劣性遺伝形式をとっていると報告している。しかしながら明らかな遺伝的証明はなされていない。
4.症状
通常は一側の精巣内に結節を触知したり、無痛性の精巣腫大で発見される。下腹部や肛門、あるいは陰嚢の鈍い痛みや重たい感じを伴うこともある。
時には、肺や骨、頚部および後腹膜リンパ節などへの転移により発見されることもあり、それに伴う症状をみることもある。
精巣腫瘍の内、男性ホルモンを分泌する性腺基質由来の腫瘍は稀ではあるが、小児例では男性ホルモンの過剰分泌のための性的早熟ををみることがある。また、以下に述べる腫瘍マーカー(HCG)の過剰分泌のため、成人で女性化乳房を生じることがある。
5.診断
精巣腫瘍は、経験のある泌尿器科医であれば触診のみで診断がつくことが多いが、精巣内 の腫瘍であることを明らかにするためには、超音波検査が最も有用である。
精巣腫瘍は後腹膜リンパ節や肺に転移しやすく、転移の有無を診断するためには、胸部レ線撮影(CTを含む)や腹部CTなどが必要である。
また、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)やアルファフェトプロテイン(AFP)などの腫瘍マーカーを測定することも、組織型や精巣摘除術後 の病状を把握するために重要である。
精巣は生命の源を産み出している場所であるため、精巣腫瘍は他臓器の腫瘍とは異なり、組織型は多種多様であり、組織型によりその治療法や予後も異なる。
組織型の診断は顕微鏡 レベルでしかなされないため、精巣腫瘍患者に対しては、たとえ遠隔転移を有していても、診断的意味をも含めまず精巣摘除術が施行される。
6.組織型
精巣腫瘍は大きく分けて、生殖細胞由来の胚細胞腫瘍と、性腺基質由来およびその他からなる非胚細胞腫瘍とに2分される。
胚細胞腫瘍が大部分(90~95%)を占めるが、胚細胞腫瘍には造精(精子を作る)細胞形成の要素が分化して腫瘍化したセミノーマと、胎児形成や胎盤形成の要素が分化して腫瘍化した胎児性癌、奇形腫(奇形癌を含む)、絨毛癌などの非セミノーマとの2型に分けられる。
なお、セミノーマと非セミノーマの混合腫瘍は非セミノーマとして扱かわれている。
性腺基質由来の腫瘍は稀であるが、間質細胞由来のライデイヒ(Leidig)細胞腫およびセルトリ(Sertoli)細胞腫がある。
7.治療
1)年齢と組織型、および予後との関係
精巣腫瘍の組織型は年齢との関係が強く、生下時から10歳頃までに発症する精巣腫瘍は奇形腫であることが多く、一般に良性と考えられ、予後は良好である。
また、小児では白血病の精巣浸潤も時に見られ、白血病の治療効果や病態を調べるために精巣生検が行われることがある。
20~35歳頃に発症する精巣腫瘍は胎児性癌であることが多く、プラチナ製剤の有効性が発見されるまではその予後は極めて悪く、進行症例ではほとんど全ての患者が2年以内に命をなくしていた。
しかし、米国のEinhornらが精巣腫瘍に対するプラチナ製剤の治療効果に着目し、1977年にプナチナ製剤を含む多剤併用療法であるPVB療法*1の有効性を報告して以来、その治療成績は革命的な向上を来たした。現在では、PVB療法よりも副作用が少なく、有効性が高いことが証明されているBEP療法*2が第I選択の治療法として一般に使用されている。
*1 PVB療法:Cisplatina, Vinblastine, Bleomycineの3者併用療法
*2 BEP療法:Bleomycine, Etoposide, Cisplatineの3者併用療法
2峰目の好発年齢の後半部分である35~40歳の精巣腫瘍にはセミノーマが多い。
セミノーマは従来より放射線治療が有効であることより、比較的予後良好なものとされてきた。
セミノーマはプラチナ製剤を中心とした化学療法に対しても最も感受性が高いため、今日ではほとんどの症例が、たとえ全身転移を有していても治癒可能なものとなっている。
50歳以上の高齢では悪性リンパ腫の精巣内浸潤であることが多く、組織診断がついた後は、全身性の悪性リンパ腫の治療を行う。
その他、稀な組織型ではあるが、絨毛癌は20~30歳台に多く、卵黄嚢(Yolk sac)腫瘍は幼児の他、成人の混合腫瘍の一つとしてみられることがある。
非セミノーマは胎児性癌、奇形腫、卵黄嚢腫瘍、絨毛癌およびこれらの組み合わせからなっている。精巣腫瘍には特徴的な腫瘍マーカーであるヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)とアルファフェトプロテイン(AFP)がよく知られている。
HCGは絨毛上皮に存在するsyncytinotrophoblastic cellで産生され、絨毛癌では100%、胎児性癌では40~60%の患者で高値を示し、セミノーマでもHCGのβサブユニット(βHCG)のみが高値を示すことが約10%あるとされている。
一方、AFPは胎児では卵黄嚢で、生後は肝臓で産生され、胎児性癌や奇形癌、卵黄嚢癌の患者で高値を示すが、純粋なセミノーマや絨毛癌では正常である。
それ故、セミノーマであるとの組織学的診断がなされても、AFPが高値を呈していれば、非セミノーマとして扱い、加療が必要である。
非セミノーマの中で最も転移の可能性が低いのは奇形腫で、高いのは絨毛癌である。その他の組織型はその中間と考えてよい。
性腺基質由来の腫瘍は稀である。間質細胞腫は成人に多く、大部分は良性である。
2)病期と組織型による治療法のまとめ
精巣腫瘍は以下の病期に分けられ、病期と組織型により治療法が異なる。
病期I:精巣のみに腫瘍は限局
セミノーマ:
通常は精巣摘除術のみでよい。
非セミノーマ:次の内の一つを行う
(1)精巣摘除術のみで、以後注意深く再発の有無を経過観察。
(2)精巣摘除術後に、後腹膜リンパ節郭清を行う。
病期II:腹部のリンパ節に転移がある。
セミノーマ:
(1)小さなリンパ節転移の場合は精巣摘除術後、体外放射線照射を行う。
(2)大きなリンパ節転移の場合は精巣摘除術後、全身化学療法あるいは体外放射線照射を行う。
非セミノーマ: 次の内の一つを行う
(1)精巣摘除術後、腹部リンパ節郭清術を行う。その後の経過観察で再発が疑われれば、直ちに全身化学療法を行う。
(2)精巣摘除術後、腹部リンパ節郭清術および全身化学療法を行う。その後経過観察とする。
(3)精巣摘除術後、全身化学療法を行う。化学療法後のレ線撮影で腫瘍の残存が認められれば、直ちに摘除術を行う。
(4)症例によっては、精巣摘除後、リンパ節郭清をせずに全身化学療法のみとすることもある。
病期III:腹部のリンパ節を越えて(肺や肝臓など)転移がある。
セミノーマ:
精巣摘除術後、全身化学療法。
非セミノーマ:
次の内の一つを行う。
(1)精巣摘除術後、全身化学療法(新しい化学療法を試行)。
(2)精巣摘除術後、全身化学療法を行う。残存腫瘍があれば、摘除術を行う。その後も腫瘍が残っていれば、全身化学療法を追加。
(3)精巣摘除術後、自家骨髄移植や末梢血幹細胞移植の併用による大量全身化学療法を行う。
なお、全身化学療法は通常4週間を1コースとしたスケジュールで行い、予防的投与では2コース、治療のためには3~6コース行う。副作用が強いために通常入院下で治療を行っており、3~6ヶ月以上の入院が必要となる。
3)手術(後腹膜リンパ節郭清術)の合併症
神経切断による逆行性射精(精液が膀胱内に流れ込む)。
4)全身化学療法(プラチナ製剤中心)の合併症
腎機能障害、骨髄障害(白血球減少、赤血球減少、血小板減少、など)、吐気・嘔吐、下痢、神経障害、脱毛、心機能障害、肺線維化症、精子産生障害など
8.患者さんへ
精巣腫瘍は肺転移巣や後腹膜の大きなリンパ節転移巣巣が先に見つかり、その原発巣の検索過程で発見されることがしばしば経験されるが、多くの精巣腫瘍は計画された治療を行うことにより、今日では救命可能となっている。それ故、たとえ進行性の精巣腫瘍であると診断されても、長期に渡る辛い苦しい治療ではあるが、有効と判断されれば、途中で治療を受けることを決して諦めないことが大切である。
9.治療成績
当科における精巣腫瘍の概要および治療成績(1999年4月時点)
1987年8月から1997年7月の10年間に当科で手術をした精巣腫瘍のうち病理学的に胚細胞腫瘍と診断されたのは37例であった。
その概要および治療成績は以下のごとくであった。
1)年齢は平均31歳(16~52歳)で、セミノーマ症例と非セミノーマ症例の平均年齢はそれぞれ35±8.4歳と26±6.4歳で、セミノーマ症例の方が有意に高齢であった。
2)主訴は無痛性陰嚢内腫瘤が最も多く70.3%(26/37例)を占めた。
3)患側は右側16例、左側20例、両側1例であった。
4)3例に停留精巣を合併していた。
5)病理組織学的分類は以下の如くである。
| 単一組織型 | 22例(59.5%) |
| 1)セミノーマ | 20例(54.1%) |
| 2)成熟奇形腫 | 1例( 2.7%) |
| 3)悪性化奇形腫 | 1例( 2.7%) |
| 複合組織型 | *15例(40.5%) |
| 1)胎児性癌+奇形腫 | 4例(10.8%) |
| 2)絨毛癌+その他の組織型 | 2例(5.4%) |
| 2)絨毛癌+その他の組織型 | 9例(24.3%) |
| * 全例絨毛癌を含む |
| 6)組織診断と病期は以下の如くである。 | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Total | |
| セミノーマ | 15 | 3 | 2 | 20 |
| 非セミノーマ | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Total 23 | 7 | 7 | 37 | |
7)37例全体の疾患特定5年生存率は94.4%であった。
8)セミノーマ症例の5年生存率は100%、非セミノーマ症例の5年生存率は87.8%であった。
9)病期Iと病期IIを合わせた症例の5年生存率は100%、病期IIIの5年生存率は62.5%であり、両者間に有意差を認めた。
10)非セミノーマ症例について、AFP5,000ng/ml以上あるいはβHCG1,000ng/ml以上の症例の5年生存率は40%であり、その他のものは100%と有意差を認めた。
10.今後の展望
米国では1970年以前は精巣腫瘍の50%以上の患者が死亡していたが、1996年には死亡率は10%以下となっている。
我が国においても同様であり、多くの精巣腫瘍はプラチナ製剤を中心とした多剤併用療法に対する感受性が極めて高く、治療成績はめざましく向上している。
それ故、今日では、如何にして治すかではなく、如何にして患者の生活の質(QOL;quality of life)を保った治療法を選択するかに、治療の主眼がおかれるようになっている。
精巣腫瘍は生殖年齢に好発するため、化学療法開始前に精子保存を行ったり、以前の手術では必発と考えられていた逆行性射精(精液が外に出ずに、膀胱内に流れる)を予防する手術法の開発など、生殖機能保存を重視した治療法が開発されている。
一方、難治性精巣腫瘍の治療については、大量の化学療法が必要なため、治療中一時的に骨髄機能が完全になくなることが予想される場合には、自家骨髄移植や末梢血幹細胞移植の併用が試みられてきているが、これらは当院でも可能な治療法であり、適応症例に対しては今後積極的に施行していきたいと考えている。