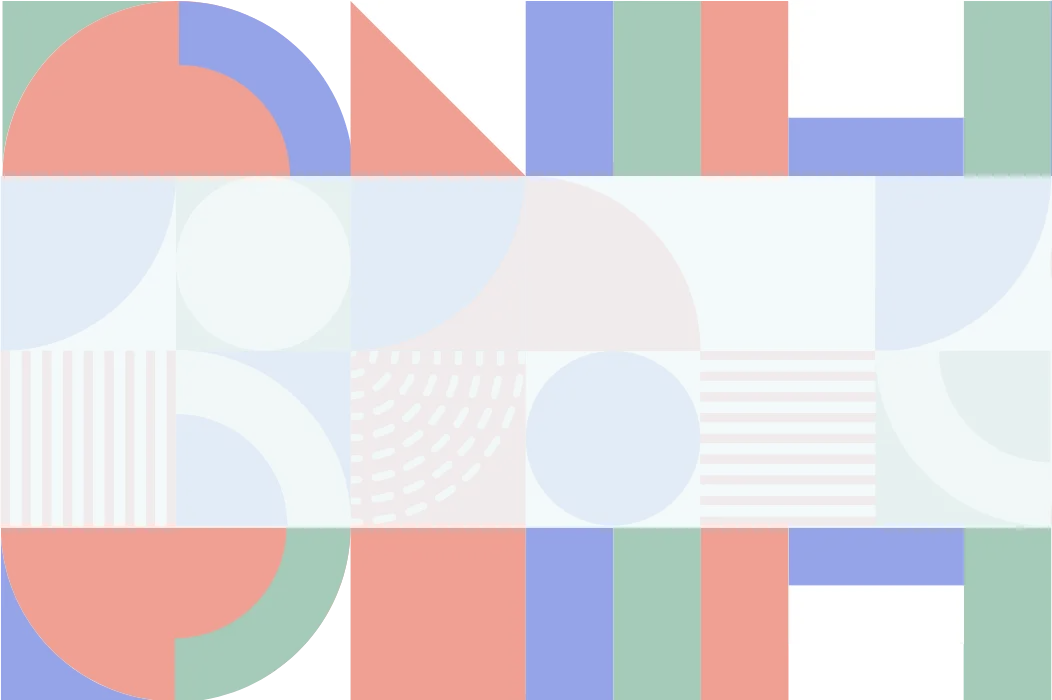卵巣がん(婦人科)
1.解剖
卵巣は拇指頭大のソラマメ型で白色の臓器で、子宮の両側で卵管の後ろ、下側にあって、腹膜(広間膜といいます)に付着しています。
卵巣を顕微鏡で観察しますと、表層を覆っている被覆上皮(腹膜由来のもので表層上皮)の直下には多数の卵胞が存在し、その中心には生殖細胞(胚細胞)である卵細胞があり、その周囲を顆粒膜細胞および筴膜細胞とよばれる性ホルモンを作る細胞が取り囲んでいます。卵巣の働きの重要なものは女性ホルモンを分泌することと卵細胞を成熟させて排卵することであり、思春期から更年期までの性成熟期には卵胞ホルモン・黄体ホルモンと呼ばれる2種類の性ホルモンを分泌して女性の機能を調節しています。
2.卵巣がんとは
卵巣は腫瘍の宝庫といっていいほど数多くの種類の腫瘍が発生します。
上に述べたように卵巣は表層上皮、胚細胞、性ホルモンを分泌する細胞とこれらの組織の間にある間質細胞から成っていますが、これらのすべての部分から腫瘍が発生するため多くの種類の腫瘍が発生することになります。
一般的には腫瘍は良性腫瘍と悪性腫瘍に分けられますが、卵巣から発生する腫瘍には良性のもの、悪性のもの(がん)以外に組織学的には良性に近い所見でありながら悪性腫瘍と似た経過を示す境界悪性腫瘍または低悪性度腫瘍と呼ばれる群が存在しており、卵巣腫瘍の取り扱いを複雑なものとしています。
表層上皮性のものとしては漿液性腺癌、粘液性線癌、類内膜腺癌、明細胞腺癌が代表的ながんで、多くは50才台に最も多くみられますが、粘液製腺癌は若年者に発生することもあります。
胚細胞性のものでは未分化胚細胞腫、卵黄嚢腫瘍、胎児性癌が代表的で、ほとんどが35才までの若い女性にみられます。
ホルモンを産生する腫瘍としては顆粒膜細胞腫が代表的で10才代までの若年に発生する型と高齢者に発生するタイプがあります。
この腫瘍は境界悪性群に属しますが、時に悪性の経過をとることがあります。また、卵巣には他の臓器のがんからの転移もしばしば起こます。
もっとも多いのは胃がん・大腸がんなど消化器のがんからの転移でクルーケンベルグ腫瘍と呼ばれます。
3.リスク因子と発生頻度
卵巣の悪性腫瘍のうち胚細胞性のものやホルモンを産生する腫瘍の発生原因やリスク因子は現在まで明らかにされていません。
一方、表層上皮由来のがんのリスク因子については
(1)内分泌因子
(2)環境因子
(3)遺伝因子
などがリスク因子としてあげられています。
このうち(1)の内分泌因子については排卵のときに傷ついた表層上皮が何らかの機転で卵巣の実質内へ取り込まれ、そこからがんが発生すると考えられていますので、排卵の回数が多いほど卵巣がんのリスクが高まると考えられています。
すなわち、未妊や排卵誘発は卵巣がんに対して促進的に働き、経口避妊薬(ピル)による排卵の抑制は卵巣がんの発生を抑制すると考えられており、最近の少産傾向による妊娠・分娩数の減少や授乳期間の短縮により、妊娠・授乳による無排卵期間の短縮のため卵巣がんの発生が増加する傾向にあるとされています。
(2)の環境因子については動物性脂肪の多量の摂取や喫煙があげられており、
(3)の遺伝因子については卵巣がんを発生しやすい遺伝子異常をもつ家系のあることが報告されています。
わが国における卵巣がんの発生頻度は1985年の成績で人口10万あたり5.7で欧米(米国:13.3、英国:11.1、ドイツ:11.6、スエーデン:14.9)と比べて低いといわれていますが、最近の少産傾向や食生活の欧米化などにより増加傾向にあると考えられています。
4.症状
卵巣は膣を通して外界と交通している子宮と異なり、骨盤内に存在しているため症状が出るのが遅く、進行してはじめて診断されることが少なくありません。
統計的には腹部膨満(お腹が張る)、腹痛、胃腸障害、頻尿(尿が近い)、体重減少などが多い症状ですが、これらは他の病気でもしばしば見られるもので、卵巣がんに特異的な症状ではありません。
最近では上に挙げた症状のため受診し、エコー検査で初期の間に発見される卵巣がんが増えてきており、原因のはっきりしない腹部膨満や腹痛なの症状をみたときはエコー検査を受けることが卵巣がんの早期発見につながる可能性があります。
5.検査と診断
卵巣がんの診断は内診やエコー検査によって卵巣に腫瘍があることを発見することに始まりますが、それが良性か悪性かの診断には画像診断や血液中の腫瘍マーカーの測定が行われます。
画像診断ではエコー検査、MRI、CTが行われ腫瘍の性質、進行度、転移の有無などの診断に有効ですが、良性・悪性の診断の正確な診断は75-80%程度です。
腫瘍マーカーとしては表層上皮性腫瘍ではCA125を中心としてCEA, CA!9-9, CA15-3, TPA, IAPなどの測定が行われますが、陽性率は70-80%であり、とくに初期のものでは陰性であることが少なくありません。
以上のような診断法の限界から現在ではたとえ良性と思われても5cmを越えるもの(悪性の疑いが強い例では5cm以下でも)では手術により切除し、組織学的に良性か悪性か確認する以外に方法がないわけです。
6.予防と検診
卵巣は腹腔内に隠れている臓器ですから子宮がんの検診のように細胞を採取して検診することはできません。
また、腫瘍マーカーは初期では陰性のことが多いため、卵巣がんの検診には役立ちません。現在、卵巣がんの検診法として有力視されているのは経膣エコー検査で、青森県では弘前大学を中心に経膣エコー検査による卵巣がんの検診が行われていますが、その効果についてはこれからの検討課題と思われます。
7.進行度・病期
卵巣がんの進行期は世界産婦人科連合(FIGO)によってl期からlV期の4つの進行期に分類されています。
l期
両側卵巣に限局する腫瘍
la期
一側の卵巣に限局する腫瘍:被膜破綻がなく、卵巣表面に腫瘍がない。腹水または腹腔洗浄液に悪性細胞がない。
lb期
両側の卵巣に限局する腫瘍:被膜破綻がなく、卵巣表面に腫瘍がない。腹水または腹腔洗浄液に悪性細胞がない。
lc期
一側または両側の卵巣に限局する腫瘍で、以下のいずれかを伴う:被膜破綻、卵巣表面の腫瘍、細胞診陽性
ll期
一側または両側の卵巣にあり、骨盤内に拡がる腫瘍
lla期
子宮、および/または卵巣に進展、または/および播種があるが、腹水または腹腔洗浄液に悪性細胞がない。
llb期
他の骨盤組織に進展するが、腹水または腹腔洗浄液に悪性細胞がない。
llc期
骨盤組織に進展し、腹水または腹腔洗浄液に悪性細胞陽性のもの。
lll期
一側または両側の卵巣にあり、顕微鏡的に確認された骨盤外の腹膜転移、または/および所属リンパ節転移のあるもの
llla期
骨盤外の顕微鏡的腹膜転移。
lllb期
骨盤外に肉眼的腹膜転移があり、その最大径が2.0cm以下。
lllc期
最大径が2.0cmをこえる肉眼的腹膜転移、または/および所属リンパ節転移のあるもの。
lV期
遠隔転移(腹膜転移を除く)のあるもの
1993-95年の3年間に世界中で治療を受けた患者の進行期はI期33.1%、II期8.8%、III期46.5%、IV期11.8%であり(FIGO 2000)、予後不良なIII期以上の症例が50%を越えていることは卵巣がんの早期発見の困難さを示していると言えましょう。
8.治療
卵巣がんの治療の治療はまず手術を行い、たとえ完全に摘出できなくても出来るだけ腫瘍を取り除き、術後に化学療法を行うのが基本です。卵巣がんは悪性腫瘍のうちでも化学療法がよく効く疾患ですが、組織型の種類によって効く薬が違っていますので、たとえ手術で取り除くことが不可能でも手術によって組織型を診断して抗がん剤を選択する必要があります。
1) 表層上皮性卵巣がんの治療(図1)
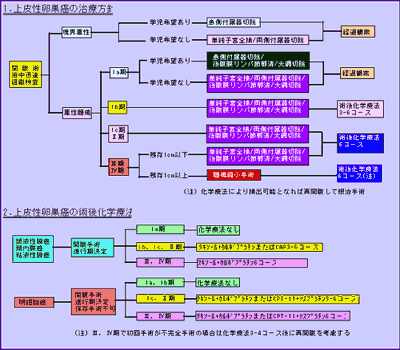
図1に進行期ごとの治療の基本を示しましたが、すべての進行期で手術と化学療法を組み合わせた治療を行うのが原則です。
イ)手術療法
漿液性腺癌、粘液性線癌、類内膜腺癌、明細胞腺癌などの表層上皮性のがんに対する基本的な手術術式は腹式子宮単純全摘出術+両側付属器切除術+骨盤および傍大動脈リンパ節郭清術+大網切除術(子宮と両側の卵巣・卵管を全部摘出し、転移の可能性がある骨盤内および大動脈周囲のリンパ節を摘出し、さらに転移の頻度が高い大網を切除する)ですが、進行期がIa期で将来妊娠を希望される場合では、明細胞癌以外のがんでは病巣が存在する側の卵巣と卵管の切除のみを行う場合もあります。
また、III期以上に進行したがんで基本術式が行えないような場合でもできるだけ腫瘍を摘出し、残った腫瘍を小さくすることが、その後の化学療法の効果を高めることになります。
ロ)化学療法
表層上皮性のがんに対する化学療法は白金製剤(シスプラチン、カルボプラチン)にいくつかの抗がん剤を組み合わせて行います。
1970年頃から最近まではCAP(シスプラチン+アドリアマイシン+シクロフォスファミド)、CP(シスプラチン+シクロフォスファミド)、JP(カルボプラチン+シクロフォスファミド)などが主に用いられてきました。
最近になってタキソール、タキソテールなどのタキサン化合物と白金製剤を組み合わせたTP(タキソール+シスプラチン)、TJ(タキソール+カルボプラチン)がCAP、CPなどよりも一次効果だけでなく生存率の点でも優れていることが明らかにされ、TPあるいはTJが表層上皮性卵巣がんの第一選択の治療法となっています。
化学療法の副作用はいずれの方法でも投与前後の吐き気や嘔吐、全身倦怠感、脱毛、四肢や関節のしびれや痛みが主な自覚症状で、他覚的には骨髄抑制(白血球減少、血小板減少)が10-14日目に見られ、程度が強い場合にはG-CSFと呼ばれる白血球の増加を促す注射や血小板の輸血が必要になる場合もあります。
図1のようにIa期では手術のみで治療を終了するのがほとんどですが、Ib期、Ic期では3-4週おきに3-6回、II期以上の例では5-6コース投与します。
表層上皮性のがんのうち漿液性腺癌、類内膜腺癌は進行例でも化学療法の効果がみられますが、粘液性線癌と明細胞腺癌は進行例では有効な薬剤がなく、これらのがんの予後が不良な原因となっています。
2) 胚細胞性腫瘍の治療(図2)
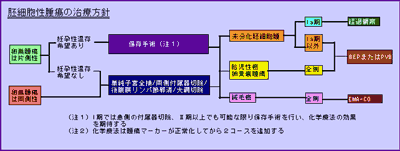
肺細胞性腫瘍のうち胎児性がんや卵黄嚢腫瘍は白金製剤を中心とする化学療法が、また未分化胚細腫は化学療法と放射線療法がよく効くことと、10-20才代の患者さんがほとんどで未婚・未産のことが多いため、進行した症例でも手術はできるだけ腫瘍のある側の卵巣・卵管の切除に留め、術後にMEP、VACなどの化学療法を行うのが一般的であり、多くの例で妊娠の可能性を温存して治癒が得られています。
なお、化学療法はAFP、hCG、LDHなどの腫瘍マーカーが正常になったから2-3コース追加するのが一般的です。
9.治療成績
日本全体での卵巣がんの集計は3年前に登録が開始されたばかりで、まだ治療成績は出ていません。そこで、世界産婦人科連合(FIGO)に世界中の主な施設より登録された成績と当院の成績を示します。
1) FIGOによる全世界の治療成績
i. 治療成績の年次推移(悪性群の5年生存率(%)
| 年度 | 例数 | 臨床進行期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la | lb | lc | lla | llb | llc | llla | lllb | lllc | lV | ||
| 1990-1992 | 7057 | 83.5 | 71.3 | 79.2 | 66.6 | 55.1 | 57.0 | 41.1 | 24.9 | 23.4 | 11.1 |
| 1993-1995 | 3409 | 89.9 | 84.7 | 80.0 | 69.9 | 63.7 | 66.5 | 58.5 | 39.9 | 28.7 | 16.8 |
ii. 1993-95年度の境界悪性群と悪性群の治療成績
| 臨床進行期 | 全症例 | 境界悪性群 | 悪性群 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | 生存率(%) | 例数 | 生存率(%) | 例数 | 生存率(%) | |
| la | 793 | 92.0 | 296 | 95.6 | 421 | 89.9 |
| lb | 91 | 88.4 | 28 | 95.9 | 46 | 84.7 |
| lc | 565 | 83.4 | 90 | 96.3 | 436 | 80.0 |
| lla | 70 | 70.4 | 6 | 100.0 | 55 | 69.9 |
| llb | 131 | 65.3 | 7 | 85.7 | 108 | 63.7 |
| llc | 185 | 64.5 | 14 | 59.5 | 154 | 66.5 |
| llla | 153 | 60.2 | 14 | 71.4 | 118 | 58.5 |
| lllb | 314 | 40.8 | 22 | 62.0 | 264 | 39.9 |
| lllc | 1567 | 28.6 | 25 | 45.0 | 1330 | 28.7 |
| lV | 507 | 17.2 | 18 | 396 | 16.8 | |
表Iのように治療成績は少しづつ改善されていますが、III期以上の進行例の予後は不良であり、そのような症例が圧倒的に多いのが問題なわけです。
iii. 表層上皮性卵巣がんの組織型別の治療成績(1993-95)
| 組織型 | 臨床進行期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l期 | ll期 | lll期 | lV期 | |||||
| 例数 | 生存率 | 例数 | 生存率 | 例数 | 生存率 | 例数 | 生存率 | |
| 漿液性腺がん | 427 | 89.4 | 153 | 65.4 | 1188 | 32.7 | 254 | 18.5 |
| 粘液性腺がん | 477 | 90.7 | 44 | 78.7 | 149 | 38.0 | 38 | 12.3 |
| 類内膜腺がん | 228 | 87.0 | 82 | 69.1 | 208 | 37.6 | 46 | 24.6 |
| 明細胞腺がん | 101 | 83.6 | 27 | 63.5 | 68 | 27.4 | 15 | 0 |
| 未分化腺がん | 56 | 81.0 | 19 | 49.8 | 103 | 29.8 | 40 | 0 |
漿液性腺がんはⅢ期の例が最も多く、その5年生存率は32.7%である。粘液性腺がんはⅠ期で発見された例が多く、Ⅰ期の治療成績は良好であるが、進行例の予後は不良である。
明細胞腺がんの治療成績はいずれの進行期でも他の組織型のがんより予後不良である。
2) 当院の治療成績(1993-1995年度治療例:悪性群のみ)
症例数が32例と少なく、他施設との比較は問題がありますが、臨床進行期別と組織型別の治療成績を示します。漿液性腺がんの成績が他の組織型のがんに比べて悪いのは進行期III期以上の例が多いためです。
i) 臨床進行期別の治療成績 ii) 組織型別の治療成績
| 臨床進行期 | 症例数 | 5年生存率 | 組織型 | 症例数 | 5年生存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| la | 17 | 100 | 漿液性腺がん | 10 | 57.14 |
| lb | 1 | 100 | 粘液性腺がん | 11 | 100 |
| lc | 10 | 100 | 類内膜腺がん | 13 | 80.88 |
| llb | 1 | 100 | 明細胞腺がん | 9 | 88.89 |
| llc | 2 | 50 | |||
| lllb | 2 | 50 | |||
| lllc | 10 | 51.85 | |||
(この期間にはIIa、IIIa、IV期の症例はなし)
IIIcの5年生存率は51.85%ですが、がんを持ちながら生存している例が半数で無病生存率は22.87%でした。
10.術後のフォローアップ
卵巣がんは治療により寛解(臨床的にがんがなくなったと判断される状態)に達しても再発する例が少なくないので厳重なフォローアップが必要です。
一般的には治療終了後1年間は1ヶ月毎、2年目は3ヶ月毎、3年目は4ヶ月毎、4-5年目は6ヶ月毎、それ以後は1年に1回の診察とし、内診、エコー検査、腫瘍マーカーの測定を行い、これらに異常があればCTやMRI検査を行います。
治療時の進行期がIII期以上の例で再発のリスクが高いと考える例では再発の徴候がなくても治療終了後1-2年間3-4ヶ月毎に念押しのための化学療法(cyclic chemotherapy)を行う場合もあります。
卵巣がんは再発も多いのですが、一方では化学療法によく反応しますので、定期的にきちんとフォローアップし、再発をできるだけ早くみつけることが大切です。