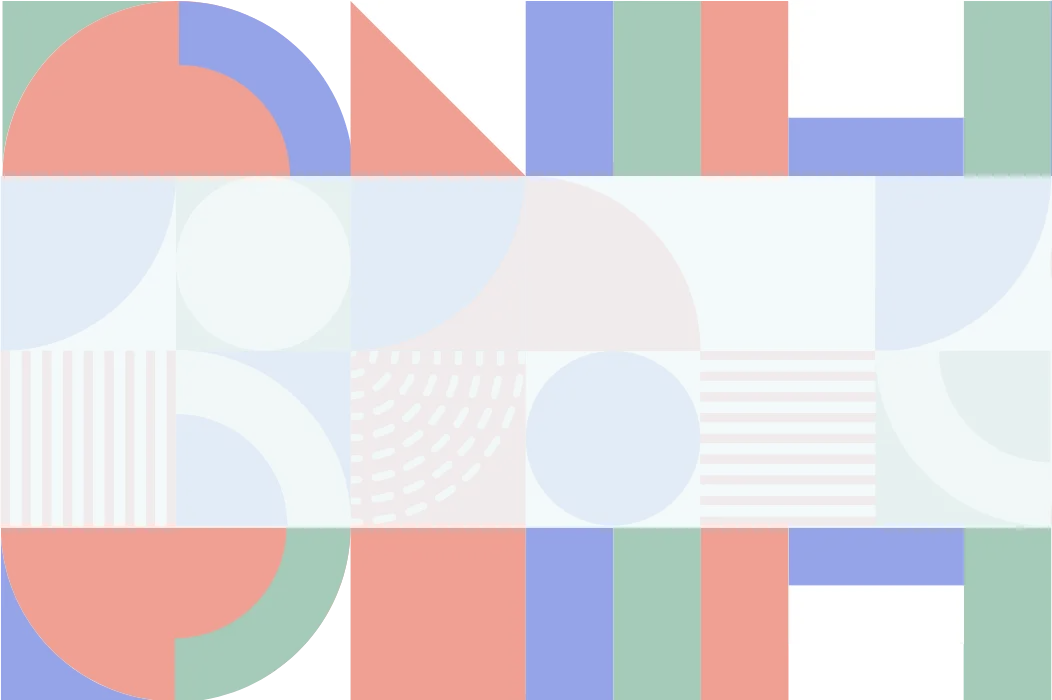子宮頸がん(婦人科)
1.概説
頚癌についてお話する前に、前癌状態、つまり異形成(前癌症)と呼ばれている状態について説明いたします。
正常な細胞から、いきなり悪性の細胞(癌)に変化するのではなく、ゆっくりと異常への変化が始まって、少し正常からはずれた細胞が出てくるようになります。これが異形成です。異形成は、その強さによって3段階に分けられます。軽度、中等度、高度の異形成です。軽度、中等度の異形成では、ふつうは定期的な検診で良いと思います。検診している間に、正常にもどる方もいますし、次第に高度に近づいていく方もいますし、そのまま同じ状態で変化なく経過する方もいます。
高度の異形成になると0期癌と区別がつかないほどのものもあり、もう少し詳しい診断や治療が必要となってきます。コルポスコープと呼ばれる拡大鏡で見ながら、変化の強そうなところを生検(小さな組織を採る)して診断するのですが、病変と思われる範囲が広い場合は、診断と治療を兼ねて、高周波による円錐切除術(LEEP)(局所麻酔で外来で施行)を行います。LEEPは取れる範囲が少し狭いのですが、これによってさらにしっかりとした診断が出来、切除した断端に病変がかかっていなければ、充分治療になる可能性もあります。
病変と思われる範囲がさらにもう少し広い場合は、入院して行う円錐切除術(LEEPよりももう少し大きな範囲を円錐形にとる手術)をすることもあります。
一旦異形成と診断されると、とにかくコツコツと検診を受けることが肝心です。
2.治療
子宮頚癌は、その進みかたによって0期からIV期までの5つの進行期に分けられます。
このうち0期(上皮内癌・・癌が頸部の上皮内にとどまるもの)とIa期(癌の浸潤が5mm以内のもの)までが初期癌とされています。これら初期癌の根治的な治療法は単純子宮全摘出術ですが、将来妊娠を希望されるなどの理由で子宮の温存を希望をされる方で、病巣の範囲が狭い場合には、円錐切除術による保存的治療も積極的に行っています(ただし、以前はIa期は3mm以内と決められていました。今は3mm以内をIa1期、3から5mmのものをIa2期として分けていまして、このIa2期の時にはより慎重に保存手術だけで良いのかどうか検討が必要です。というのも、数ミリのわずかなことなのですが、癌というのは浸潤、つまり組織への入り込みの深さが深くなればなるほど、転移してゆく率が高くなるからで、この3ないし5ミリというのが、本当に微妙な深さなのです)。また、0期で範囲がごく狭い場合には高周波による円錐切除術(LEEP)を外来で行うことも可能です。
このような子宮を残す手術の比率はどんどん増えていますが、円錐切除、LEEPで本当に手術を終えてよいのかどうかは、慎重に判断が必要です。というのも、こういった手術は、当然取る範囲は小さくなっているわけですから、十分な余裕をもって癌が取れているのかどうか、しつこいほどに確認が必要なのです。
ただし、以上は頚癌のなかでも、扁平上皮癌についてです。腺癌は初期癌の段階での診断が難しく、個別の対応が必要です。一般に腺癌は、扁平上皮癌よりも悪性度が高くて、慎重に治療しなくてはなりません。
これ以上進行した癌では、リンパ節転移などがみられるようになりますので、徹底的な治療が必要ですが、手術が可能なのは癌が骨盤壁に及んでいないIb期とII期で、III、IV期は放射線治療が第一の治療法となります。また、腺癌は扁平上皮癌よりも予後が悪く、さらに慎重な取り扱いが必要です。
Ib期とII期の手術は、癌が進展していくルートである子宮傍結合組織(子宮のまわりの組織)を含めて切除する広汎性子宮全摘出術(骨盤内のリンパ節の郭清を含む)が必要であり、また、この時期でもすでに大きく腫れた肉眼的にはっきりわかる骨盤内のリンパ節転移がみられることもあります(これは当科では術前の超音波診断で、ある程度キャッチできます)ので、このようなときには腹部の大動脈(背骨の前を走っている太い動脈)周囲のリンパ節(傍大動脈リンパ節)の郭清をも行う必要があります(子宮に近い骨盤のリンパ節に転移したあとは、次第に上の方、頭の方へと癌の細胞は上ってゆきます。骨盤のリンパ節が大きく腫れるほどに多くの癌細胞が転移すれば、その上の傍大動脈リンパ節が心配になるのは当然のことでしょう)。
但し、子宮頚癌が卵巣に転移することは稀ですので卵巣の温存は一応可能です。また、術後の組織検査で再発のリスクが高いと判断されるときには補助療法として放射線療法または化学療法を追加しますが、現在私共は癌を全身病ととらえる立場から、局所的な放射線療法も大事ではありますが、化学療法が補助療法として必要ではないかと考えています。
III期以上の進行癌では放射線治療が主治療となりますが、治療機器の進歩にもかかわらず、放射線療法単独による治療成績は改善されていません。そこで、最近ではこれらの進行癌に対して、まず化学療法を1-2コース行って腫瘍を縮小させて(普通の点滴で投薬する方法と、子宮動脈に直接薬を注入する動注療法がありますが、当科では病気の状態によってどちらも可能です)から、手術または放射線治療を行うことが試みられています。この治療法は始められてから数年しか経過していませんので予後については結論できませんが、われわれの成績では化学療法によって65%近い例で腫瘍の縮小がみられており、生存率の向上につながるのではないかと期待しています。また、このような進行癌でも、治療前の超音波診断でリンパ節転移がはっきり認められる場合とそうでない場合があり、私たちは当然治療方法にも工夫が必要であると考えて対応しています。