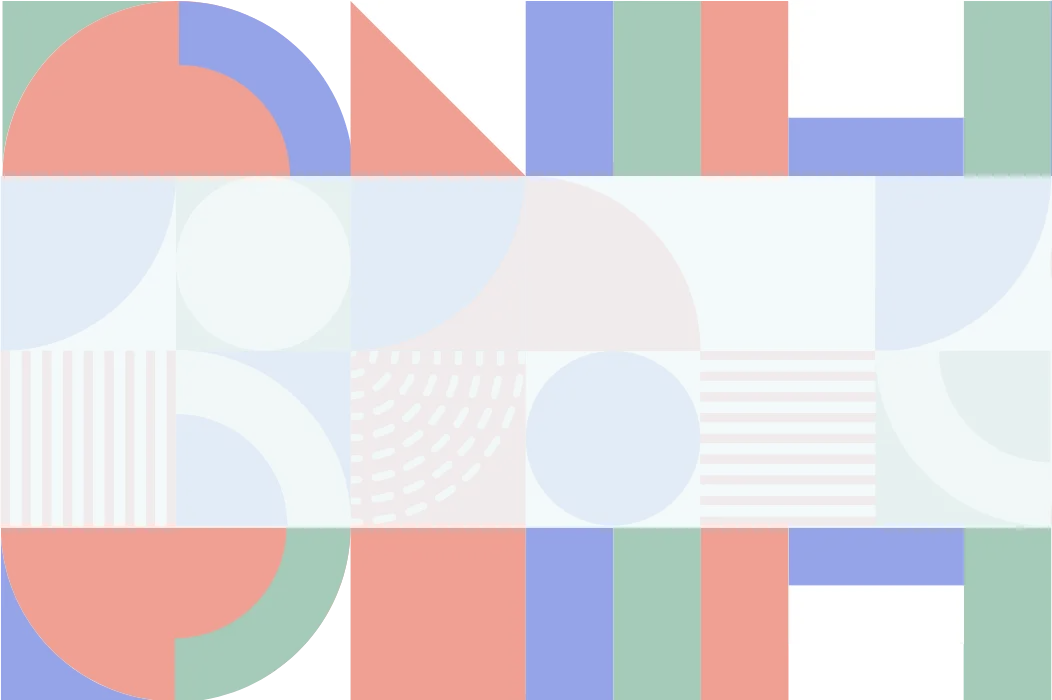よくある質問
緩和ケアについて
緩和ケアって何ですか?
緩和ケアとは、命にかかわる大きな病気がある患者さんとそのご家族のこころとからだのつらさを和らげ、生活の質を向上させるケアのことです。
「支持療法」や「サポーティブケア」といわれることもあります。
緩和ケアはがんのためだけのケアなのでしょうか?
がんだけではなく、命にかかわる病気、たとえば回復が難しい心不全やエイズの他、認知症や神経変性疾患(パーキンソン病など)、腎不全なども対象です。
特定の方にだけ提供されるものなのでしょうか?
いいえ。例えば、がんの場合には、がんと診断された時からつらさがあれば、緩和ケアを受けることが大切です。いわゆる「末期がんの人のためのもの」、ではありません。
その他の病気の場合には、病気の特徴に応じて、条件を満たす場合に提供されます。詳しくは担当医師にお尋ねください。
抗がん剤などの副作用によるつらい症状は、我慢するしかないのでしょうか?
抗がん剤などによるつらい症状がある場合には、お薬を変更したり減量する必要があります。その症状は、緩和ケアを受けることで和らぐことがあります。まずは、担当医師または看護師に「つらい症状を和らげてほしい」とご相談ください。
つらい症状がある場合、どのように相談すればよいのでしょうか?
まずは、担当医師または看護師に「つらい症状を和らげてほしい」とご相談ください。
「支持療法を受けたい」「緩和ケアを受けたい」「つらい症状の専門家に相談したい」といった表現もよいでしょう。
緩和ケアチームについて
緩和ケアチームって何ですか?
緩和ケアチームとは、緩和ケアを提供するための専門のチームです。医師、看護師、薬剤師のほか、心理士、栄養士、リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカーなどで構成されています。
緩和ケアチームから、どの様なケアを受けることができますか?
痛みや息苦しさといったからだのつらさや、不眠や気分の落ち込みといったこころのつらさに対して、お薬や看護ケア、心理面談などを通して、症状を和らげる工夫をします。経済的(社会的)な問題や、医療社会福祉サービスの利用などの相談にも対応します。
大阪医療センターに緩和ケアチームはありますか?
あります。「ケアサポートチーム」という名前で、活動しています。当院に入院中で、がん、回復が難しい心不全、エイズの患者さんとそのご家族が利用できます。
緩和ケアチームに相談したい場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
まずは、担当医師または看護師に「ケアサポートチーム(緩和ケアチーム)に来てほしい」とご相談ください。
緩和ケアチームへの相談などは誰でも利用できますか?
当院に入院中で、がん、回復が難しい心不全またはエイズの患者さんとそのご家族(入籍していないパートナーや主にお世話をされる友人知人の方を含む)は利用可能です。それ以外の方は、担当医師または看護師にご相談ください。
緩和ケアチームへの相談などは特別な費用はかかりますか?
介入期間中は1日あたり390点分(健康保険が適用:1割負担で390円、3割負担で1370円)の費用が加算されます。ただし、高額療養費制度の利用で、上限額以上の請求は行われません。
緩和ケア外来について
緩和ケア外来って何ですか?
緩和医療を専門とする医師と、がんに関わる認定または専門看護師による、専門的な緩和ケアを提供する外来のことです。
緩和ケア外来から、どの様なケアを受けることができますか?
痛みや息苦しさといったからだのつらさや、不眠や気分の落ち込みといったこころのつらさに対して、問診を通じて原因を探り、適切なお薬を処方したり、専門部署に紹介することで、症状を和らげる工夫をします。
大阪医療センターに緩和ケア外来はありますか?
あります。「緩和ケア内科」が外来を開設しています。がん、またはエイズの患者さんとそのご家族(入籍していないパートナーや主にお世話をされる友人知人の方を含む)が利用できます。
緩和ケア外来を受診したい場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
当院に通院中の方は、担当医師に「緩和ケア内科の外来を受診したい」とご相談ください。
他院に通院中の方は、担当医師に「大阪医療センターの緩和ケア内科の外来を受診したい」とご相談ください。
緩和ケア外来は誰でも利用できますか?
がん、またはエイズの患者さんとそのご家族(入籍していないパートナーや主にお世話をされる友人知人の方を含む)であれば、どなたでも利用できます。紹介状(診療情報提供書)が必要ですので、必ず担当医師にご相談ください。
緩和ケア外来は特別な費用はかかりますか?
初診料の他、診療内容や処方に応じて別途費用がかかります。なお、健康保険および高額療養費制度が適用されます。
緩和ケア外来を受診したら、今の担当医師には診てもらえなくなりますか。
いいえ。今の担当医師の診察と並行して、緩和ケア外来をご利用いただけます。
緩和ケア病棟について
緩和ケア病棟って何ですか?
患者さんのこころとからだのつらさを和らげ、生活の質を向上させるため、緩和ケアを専門的に提供する病棟のことです。
ホスピスとは違うのですか?
ほぼ同じ意味で使われることが多いですが、緩和ケア病棟は「つらい症状を和らげる場所」で、症状が落ち着けば自宅などに退院することもありますが、ホスピスは「最期の時を過ごす場所」という意味がより強くなります。
緩和ケア病棟ではどの様なケアを受けることができますか?
痛みや息苦しさといったからだのつらさや、不眠や気分の落ち込みといったこころのつらさに対して、お薬や看護ケアを通して、症状を和らげる工夫をします。リラクゼーションや特別食の提供、音楽療法やアロマセラピーなど、入院中に楽しみが持てるような取り組みを行っているところもあります。
一方で、がんを小さくする治療や、心臓マッサージ人工呼吸器装着といった延命処置など、からだに負担がかかるような治療や処置は行われません。
大阪医療センターに緩和ケア病棟はありますか?
いいえ。緩和ケア病棟はありませんが、当院入院中は、緩和ケアチーム(ケアサポートチーム)による専門的な緩和ケアを受けることが出来ます。
緩和ケア病棟で過ごしたいのですが、どの様な手続きが必要でしょうか?
緩和ケア病棟がある病院で、入棟面談や申し込み手続きを行うことが必要です。「抗がん治療を行わないことに同意している」など、入棟面談の申し込みには諸条件があります。まずは、担当医師または看護師に「緩和ケア病棟の利用について相談したい」とお声がけください。
緩和ケア病棟は誰でも利用できますか?
治療困難ながんまたはエイズの患者さんのみ利用できます。ただし、対象となる患者さんの条件は、各病院によって異なりますので、入棟面談の際に直接お尋ねください。
緩和ケア病棟の利用に、特別な費用はかかりますか?
1日あたり約5000点分(1割負担で約5000円、3割負担で約15000円)の費用がかかります。ただし、高額療養費制度の利用で、上限額以上の請求は行われません。その他、食事料金や個室料金などが別途請求されます。
抗がん剤をやめようと考えていますが、緩和ケア病棟でできる限りの治療処置をしてもらうことは可能ですか。
つらい症状を和らげるための治療や処置は行っています。どんな治療や処置を行っているかは、その病院や病状によって異なりますので、入棟面談の際に直接お尋ねください。
モルヒネなどの医療用麻薬について
モルヒネなどの医療用麻薬とは何ですか?
主にケシから作られた麻薬性の鎮痛薬の総称です。適切に使うと、がん等による強い痛みを抑える効果があります。しかし、誤った方法で使うと、依存などを起こすため、日本では麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)で厳重に管理されています。
覚せい剤や違法麻薬とは何が違いますか?
医療用麻薬は、痛みをおさえることを目的とした「医薬品」として、精製された成分から製造されており、痛み止めの効果や安全性が担保されています。もちろん、適切に管理使用すれば、罪に問われることはありません。
一方、違法に取引されている「覚せい剤」や「麻薬」は不純物が混じっていたり、成分量が不明なため、安全性が担保されていません。また、違法薬物に分類されるため、所持していると罪に問われます。
医療用麻薬を使い始めると、依存症になりませんか?
決められた量と方法を守って服用すれば、依存症にはなりません。
医療用麻薬を使用することで寿命が縮まることはありませんか?
決められた量と方法を守って服用すれば、寿命が縮まることはありません。
医療用麻薬を使い続けていると、体が慣れてしまい、いざというときに効果がなくなったりすることはありませんか?
決められた量と方法を守って服用すれば、体が慣れてしまったり、効果がなくなることは少ないことがわかっています。ただし、がんが大きくなったり広がったりすることで、これまでのお薬の量では痛みをおさえきることが出来なくなることがあります。その時は、痛みの強さに合わせて、再度お薬の量を調節します。
医療用麻薬を服用することでどんな副作用がありますか?
主な副作用は、①眠気、②吐き気、③便秘の3つです。眠気と吐き気は3割くらいの人が経験しますが、1週間前後でおさまってきます。一方、便秘は続きますので、排便の状態に合わせて便秘薬を併用します。
医療用麻薬はどのように使うのですか?
医療用麻薬は、定期的に服用してゆっくり1日中効いてくれるお薬(徐放剤)と、痛いときにだけ飲むお薬(レスキュー薬)の2種類があり、この2つを組み合わせることで、痛みをコントロールします。
医療用麻薬は飲み薬だけですか?
飲み薬のほか、貼り薬や、注射、座薬などの種類があります。からだの状態や痛みの強さ、生活スタイルに合わせて、最適なお薬を処方します。
医療用麻薬を使い始めたら、使用し続けないといけませんか?
がんの治療によって、がんが消えたり小さくなって、痛みが消えたりおさまった時には、医療用麻薬の使用を中止することもあります。
モルヒネなどの医療用麻薬を使用し始めたら、今後のことを検討しておくべきでしょうか?
医療用麻薬の使用の有無にかかわらず、「がん」などの命にかかわる病気になったときには、医療者や家族(入籍していないパートナーや主にお世話をされる友人知人の方を含む)ともしもの時のことについて話し合っておくようにしましょう。
なお、医療用麻薬を使用すると、車の運転や高所での作業等ができなくなるため、移動手段や仕事内容の変更を余儀なくされる場合があります。今後の生活について考える必要が出てきます。
「麻薬」という言葉にどうしても抵抗感を覚えるのですが、できるだけ医療用麻薬には頼らずに我慢するほうが良いでしょうか?
患者さんの気持ちや生活スタイルに合わせて、できるだけ医療用麻薬を使わずに症状を和らげる工夫をすることはできます。ただし、痛みがとり切れず、生活のしづらさが出たり、食事や運動が十分にできずにがん治療に支障がでる場合には、医療用麻薬の使用を推奨します。
痛みが増してきたので処方される医療用麻薬の量を増やしてほしいのですが、どの程度まで増やせますか?
痛みの強さや、痛みを和らげるのに必要な医療用麻薬の量には、個人差があります。投与量には上限がなく、効き具合や副作用を見ながら、一人一人に合った量に調節します。
医療用麻薬はがんに効果はあるのでしょうか。
医療用麻薬に、がんを消したり小さくする効果はありません。しかし、がんによる痛みを和らげる効果はあります。
痛みやしんどさを何とかするには、どうしても緩和ケア外来や緩和ケアチームを利用する必要があるのでしょうか。
緩和ケア外来や緩和ケアチームを利用しなくても、担当医師が痛み止めなどを処方することもできます。まずは、担当医師または看護師につらい症状をお話しください。
闘病生活における気持ちのつらさだけでも、緩和ケア外来や緩和ケアチームを利用することはできるのでしょうか。
はい、可能です。必要に応じて、心理療法や精神科医師との面談など、専門的なケアをご紹介することもあります。まずは、担当医師または看護師につらい症状をお話しください。
レスキュー薬はどうして回数制限がないのですか?
痛みの強さや、痛みを和らげるのに必要な医療用麻薬の量には、個人差があります。痛みを我慢せず生活できるよう、レスキュー薬の使用回数制限は設けられていません(一部の薬剤を除く)。レスキュー薬を使った回数や時間帯を見ながら、一人一人に合った量に調節していきます。
医療用麻薬の副作用が心配で、服用に不安を感じています。
心配なことをお聞きしながら、少ない量から開始したり、比較的副作用が少ないタイプの医療用麻薬を選んだりして、少しでも安心して使えるように工夫します。
医療用麻薬を使用していても、旅行や出張に行けますか?
車を運転しなければ、旅行や出張に行くことは可能です。ただし、海外に行くときには、医療用麻薬を所持していることに対して、各地域の厚生局を通じてあらかじめ渡航国の許可を取っておくことが必要です。申請から許可が下りるまでに約2週間ほどかかります。海外旅行や出張に行くことが決まったら、すみやかに担当医師にご報告ください。