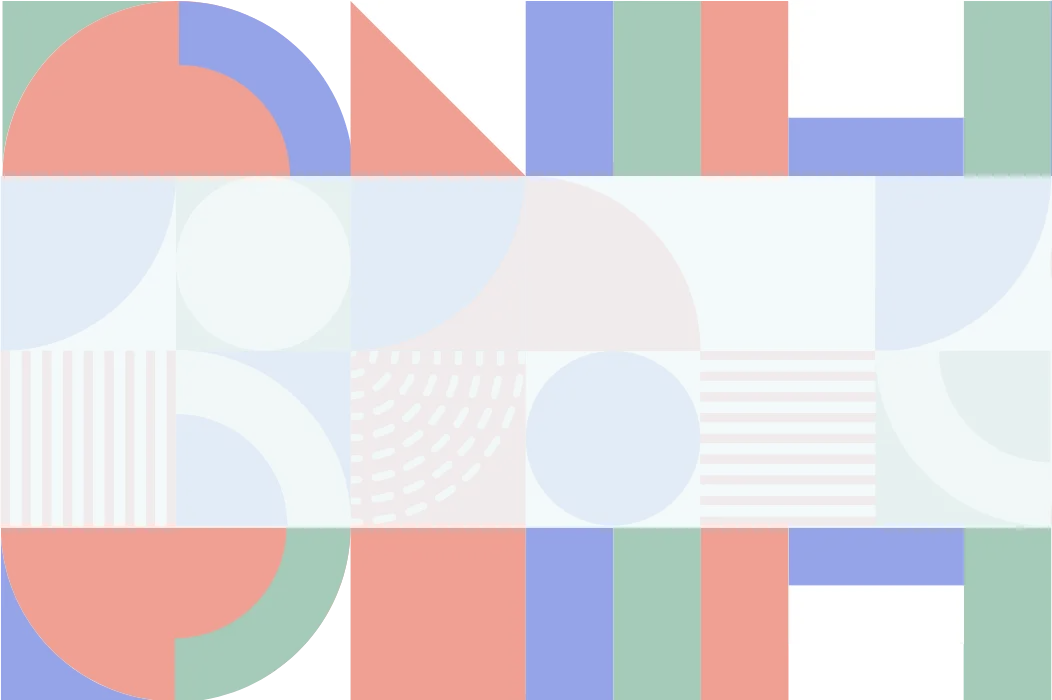宮本 敦史 医師
医学の未来に貢献できるような
リサーチマインドをもった医師を育てます

肝胆膵外科 科長 宮本 敦史 医師
医療はまだまだ未知の領域が多い世界。医師に必要とされるのは、自ら課題を見つける力。そして、どうすれば解決できるのか、もっと良い方法はないかという探求心。その先にしか医療の進歩はないのです。自身もそういった気概を持つ医師であり続けたいと思うと同時に、強い探求心を持った医師を育成していきたいと考えています。
「人の役に立つ仕事をする」という思いから、医療の道へ
私が「医者になる」とはじめて言葉にしたのは、中学校3年生の時。担任の先生から小言混じりに「もっと人の役に立つことを考えなさい」と言われ、悔しまぎれに「医者になって難民援助に行く!」と言い返した。面白いもので、その言葉が思いがけず現実となり、医師になってから27年が経ちました。
今でこそ内科でも内視鏡やカテーテルによる治療が行われるようになっていますが、私が学生だった当時は、内科は診断のみで、手術をはじめとする「治療」は外科が行うという時代でした。外科の道に進むことを選んだのは、多くの外科医がそうであるように自分の手で人を治したいと思ったから。消化器外科を選び、やがて肝胆膵外科の専門医になりました。

私の医師としてのキャリアは少々変わっています。これまでの医師人生の中で、大学病院での研究職や行政職である厚生労働省の医系技官も経験しました。2007年に大阪医療センターに入職して今に至りますが、さまざまな立場を経験した中で感じるのは、患者さんが元気になって社会復帰する姿を見ることができる臨床医は、やはり医師としてのやりがいに満ちた仕事だということ。また、当センターは、仕事だけではなく、趣味でもつながりあえる人間関係がつくれる職場であることも私にとってはうれしいことでした。
自分の判断で診療を進めていける研修環境を提供
肝胆膵領域の悪性疾患は難治がんであり、専門的な知識と高度な技術が必要とされる上、手術そのものが技術的に上達することが難しい分野です。しかし私自身は、取り組むべき価値がある分野と感じ、可能性を追求するために、あえてそこを目指すことに。多くの研修医の皆さんにも、外科医にしか成し得ない肝胆膵領域がんの治療に果敢にチャレンジし、術者として活躍できるようになってほしいと思います。
私が研修医に求めることは「自主・自立」です。自分で考え、行動すること。すぐに答えを教えるのではなく、まずは自主的な判断のもととなるヒントを与えて見守ることを、可能な限り心がけています。自立した医師に成長してもらえるよう、自分の判断で診療を進めていける研修環境を提供しています。

専修医海外留学制度など各種研修制度も充実
日本肝胆膵外科学会では、高難度手術を多数実施している施設を「高度技能専門医修練施設」として認定しています。当センターもそのひとつ。このような環境で、研修医として手術や治療を学べることは、当センターの大きな特徴です。また、その一方で、腹腔鏡を用いた低侵襲外科手術も積極的に行い、腹腔鏡下胆嚢摘出術は毎年100例以上実施。研修医が幅広い経験を積むことができる環境となっています。手術が主体となる大学病院とは異なり、主治医として診断の初期から終末期まで一人ひとりの患者さんの診療に主体的に関わることができるのも大きな魅力ではないでしょうか。

全国で143施設ある日本最大の病院グループ・国立病院機構は、「診療」「研究」「教育の実践」という3つの柱で成り立っています。機構全体としての研修も非常に充実しており、約1ヶ月間、後期研修医が米国の医療現場を体験する「国立病院機構(NHO)専修医海外留学」や、所属病院とは異なる機構病院に若手の医師が一定期間留学できる「NHOフェローシップ制度」など、スキルアップをめざす医師にとって有益な制度が数多く用意されています。
私が専門とする肝胆膵領域のがん治療においては、科学的根拠に基づく治療法の開発が進んできましたが、未だ十分とは言えません。手術の技術習得だけでなく、まだ解明されていない領域や症例などに対しても強い探究心を持ち、知識も技も貪欲に吸収してほしいと思います。私たち指導医は、学びたい意欲のある人へのサポートを惜しみません。